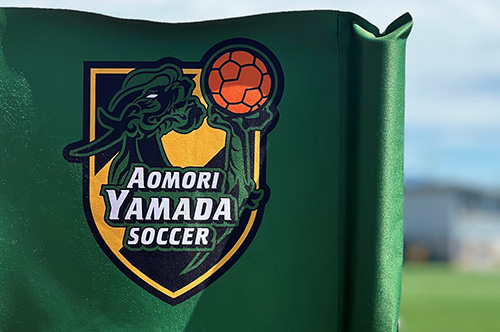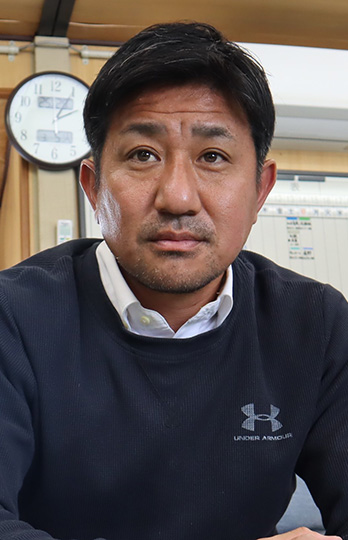ケガをしない身体づくりが大事
正木監督の信条は、昔も今も変わりません。現役時代はケガに悩まされ、可能性のあったプロ入りも叶いませんでした。アキレス腱の断裂、膝の半月板には3回メスを入れ、足首も1回手術しています。だからこそ、ケガの予防には徹底してこだわっているのです。
「チームのフィジカルトレーナーに伝えているのは、何よりも『ケガをしない身体づくり』です。高校は実質3年間もなく、2年10カ月ほどです。そのうち、3カ月も離脱すれば、相当なダメージになります」
今春、入学してくる新入生たちにもすでにトレーナーからメニューを送っているようです。QRコードを読み取れば、確認できる仕組みになっています。
「基礎の土台ができていなければ、簡単に崩れてしまいますから」
毎年、全国各地から有能なタレントたちが集まってきますが、北国の環境に慣れていない選手たちは春先まで冷え込む青森の外気はこたえるようです。気温が低ければ低いほど、故障のリスクも高まります。
「寒さは無視できないです。筋肉系のケガは目につきます。特に内転筋を痛める選手が多いですね。どれだけ身体を温めても、猛吹雪のなかでも練習をするので、冷えてしまうんです。秋から冬にかけては、ケガ人が増える傾向にあります」
トラブルが多い内転筋はもちろんのこと、体幹、腰回り、腸腰筋は入念に鍛えています。試合翌日の月曜日はリカバリーメニューと筋力トレーニングをこなします。火曜日は完全オフとなり、水曜日はフィジカルトレーナーのもとで、コーディネーショントレーニングを取り入れています。
「ケガをしない身体の動かし方、使い方もすごく大事です。例えば、トップスピードから急にストップする、止まったところから急に動く、あとは方向転換もそう。ケガは自らアクションを起こすときよりも、相手の動きに対して、反応するリアクション動作のときに発生しやすいので」
最近、正木監督が気になっているのは、身体の硬い選手が多いこと。ひと昔前の選手たちに比べると、股関節などの可動域が狭くなっている印象を受けています。
「無理な体勢でボールを蹴ることができないなって。腰が回らないんですよ。幼少期から恵まれた環境で育っている選手が多く、野性味あふれる選手が少なくなっている気がしますね。昔は木登り、鬼ごっこなどで自然と学んだ動きです。今後はもっと柔軟性を持たせるように促していきたいと思っています」
正木監督が高校年代の指導者として、いま切に願うのは小中学年代からコンディネーション能力を向上させること。「上のカテゴリーで輝くための重要な要素となり、さらにはケガの予防にもつながってくる」と言葉に力を込めていました。