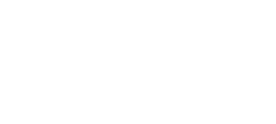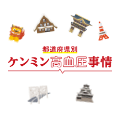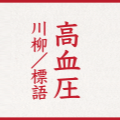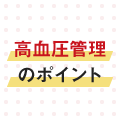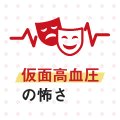郷土愛にあふれ、「調和」を大事にする
福島県民
東北地方には、秋田県や青森県など文化的に特徴のある場所が多いのですが、福島県は東北地方の中でも関東に近い場所に位置しているためか、「東北らしい独特さ」のようなものは比較的マイルドな地域だと思います。秩序や規律を重んじ、自己主張も控えめで、「みんな仲良くやっていきましょう」というように、周りとの調和を大事にする県民性があります。福島県は東西に広く、太平洋沿岸部の「浜通り」、内陸部の「中通り」、山に囲まれた「会津」という、3つの地域があり、県民性も地域によって異なります。「浜通り」は漁師町なので、船乗り気質で開放的な性格の人が多いと思います。「中通り」は交通の便が良いため、大学や会社の支店などが多く、よそから入ってくる人が多い地域で、バラエティ豊かな人が集まっています。「会津」は伝統を守り、情に厚く頑固な性格な人が多いようです。どの地域に住む人も、「郷土愛」が強く、地域のつながりや仲間を大切にする心の優しさを持ち合わせているのが福島県の特徴です。
きましょう」というように、周りとの調和を大事にする県民性があります。
福島県は東西に広く、太平洋沿岸部の「浜通り」、内陸部の「中通り」、山に囲まれた「会津」という、3つの地域があり、県民性も地域によって異なります。「浜通り」は漁師町なので、船乗り気質で開放的な性格の人が多いと思います。「中通り」は交通の便が良いため、大学や会社の支店などが多く、よそから入ってくる人が多い地域で、バラエティ豊かな人が集まっています。「会津」は伝統を守り、情に厚く頑固な性格な人が多いようです。どの地域に住む人も、「郷土愛」が強く、地域のつながりや仲間を大切にする心の優しさを持ち合わせているのが福島県の特徴です。
野菜をたくさん食べるのに「肥満」が多いのはなぜか
都道府県別死亡率ランキングを見てみると、福島県では心疾患の死亡率が高く、中でも急性心筋梗塞の死亡率は男女ともに全国1位です。平均寿命も男性80.12年で41位、女性86.40年で43位と低迷しています。
私が心疾患の多さに加えて問題視しているのは、福島県民の「肥満」です(都道府県別BMI※1の平均値:男性2位、女性1位)。その原因として、運動量の少なさや、塩分や油分の多い食事など、「生活習慣」が大きく関連していると考えられます。運動量が少ないのは、どうしても車に頼る生活になってしまっている人が多いためでしょう(人口100人あたりの自動車保有台数ランキング:福島県全国8位)。福島県に限らず、日本の「地方」はどこも同じだと思いますが、車社会で運動量が少ないと、どうしても肥満になりやすくなります。
また、食事面にも問題があります。福島県は農業が盛んで農作物が多く採れるため、新鮮な野菜が手に入りやすく、男女ともに全国2位の野菜摂取量です。野菜をたくさん食べるのは大変良いことなのですが、問題なのは調理方法のようです。食塩摂取量を見てみると、男女ともに全国2位で、全国平均を上回っています(福島県の食塩摂取量:男性11.9g/日、女性9.9g/日)。ちなみに、日本高血圧学会のガイドラインでは、1日当たりの食塩摂取量の目標は「6g未満」と設定されており※2、福島県の食塩摂取量はその目標値を大きく超えてしまっているのです。また食塩摂取に加え、福島県では「食用油」の摂取が多いのが肥満の原因として気になります。それらの摂取を控えた食事を心掛け、「過食しない」ことが大切です。また、福島県民に限った話ではないですが、今までに根付いた生活習慣を変えるのはなかなか簡単なことではありません。それでも、自身の健康のために、運動面・食事面の両面から一度見直してみてほしいと思います。
※1 身長と体重のバランスから肥満度を判定する数値。BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)の数値で表す。BMI 25以上は「肥満」と定義されている。
※2 厚生労働省の1日あたりの塩分摂取量の目標値は男性8g、女性7gですが、ここでは減塩の観点から日本高血圧学会のガイドラインの目標数値を引用しております。
3つの地域で健康意識にも差がある!?
先ほどお話ししたように、「浜通り」、「中通り」、「会津」でそれぞれ特徴があるのですが、健康意識にも地域差があります。「浜通り」には港町特有の「あまり細かいことを気にかけず、自分の健康にもおおらかな人」が多い印象です。特定健診受診率を見ても、他の地域よりかなり低いのはそのためです。福島県全体の特定検診受診率は41.12%ですが、「浜通り」のいわき市では32.25%ですから、その受診率の低さは福島県の中でも際立っています。
逆に、「中通り」や「会津」は予防医療の認知が進んでいるということもり、健康意識も高いように感じます。

福島県国民健康保険団体連合会「特定健康診査の状況」のデータをもとに作成
「浜通り」で健康意識が高まらない要因として、県民性だけでなく、医療・保健の従事者の数の問題もあります。以前から少ない地域であるのに加えて、東日本大震災や原発事故後の減少の影響がいまだに残っているのです。特に、「浜通り」の中心都市いわき市では、病院の病床当りの常勤医数が中核市の中で最も少ないのが現状です。住民の健康意識が低いのは、医療・保健における人的資源供給面の問題でもあるかもしれません。住民に正しい知識や健診の意義を十分に伝えられなければ、健康意識を高めることはできませんので。
このように、3つの地域によって住民の意識も違えば、医療面での状況も異なるので、地域ごと、またはもっと細かい医療圏ごとで考えなければいけないというのが、福島県の健康問題を考える際の難しさですね。

特定健診の重要性
予防医療の観点からすると、特定健診を受けることはとても大切で、健診を受けることで未然に防げる病気もたくさんあります。例えば、福島県では糖尿病における死亡率(男性11位、女性9位)や透析導入率も高い傾向にありますが、健診で糖尿病予備軍を早く見つけ出し、重症化させないようにすることでこれらはある程度予防できるのです。
現在、被扶養者(配偶者)の特定健診・保健指導の受診率の低さが、全国的にも問題になっていますが、福島県ではその低さが顕著です。健診を受けずにいることで病気の発見が遅れている可能性があります。また、福島県の被扶養者の特定保健指導の受診率は「1割以下」ですが、これが生活習慣の改善の障害になっていると思います。会社員であれば、健診について職場である程度周知されますが、被扶養者となると、健診を受けられること自体を知らない方もいるようです。皆さんには、自身の健康はもちろん、被扶養者の健康も、毎年の健診でできちんと管理していってほしいと思います。また、健診の受診は、家族で「健康づくり」について考える、「良いきっかけ」にもなりますよ。
「どうしてやらなければいけないのか」という動機付けが大事
いまの時代、新聞、雑誌、テレビ、インターネットなど、たくさんの情報メディアがあり、健康に関する情報があふれています。しかし、その情報の中には、間違った情報も含まれており、注意が必要です。情報メディアが多岐にわたるなか、本当に正しい情報をわかりやすく県民の皆さんに伝えるためにはどのような手段が効果的なのか、私たち医師も頭を悩ませています。
日々の家庭での血圧測定は、自分でできる最も簡単な健康管理法ですが、「なぜ血圧を毎日測る必要があるのか」をちゃんと納得してもらえなければ、測定を継続させるのは難しいでしょう。健診についても同じで、「なぜ健診を受ける必要があるのか」をまず理解してもらう必要があります。人はしっかりと胸の内で「動機付け」ができなければ行動に移しづらいものです。医療従事者が患者さんに対面して説明することも重要ですが、行政や地域コミュニティ、賛同してくれる企業などとも協力し合い、もっと多くの方に向けて積極的に健康情報を発信していくべきだと感じています。
県民の健診・保健指導受診と健診で異常のあった方の医療機関への早期受療の「動機付け」のための行政、医療・保健団体と医療機関が連携した活動が福島県の各地域でも漸く始まっています。今後の効果を期待したいと思います。

さいごに
福島県民は、地域の輪を大切にし、人とのつながりを大切にします。その優しさをもって、自分の周りの大切な人に「健康の輪」を広げていきましょう。自分の健康だけでなく、家族も健康に、そして地域も健康にしていけたらいいですね。そのために、まずは毎年の健診受診から始めてみませんか?
参考
厚生労働省「国民生活基礎調査」
厚生労働省「人口動態調査」
厚生労働省「患者調査」
厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況」
自動車検査登録情報協会 統計情報
福島県国民健康保険団体連合会 各種統計資料
健康ふくしま21計画
新生ふくしま健康医療プラン