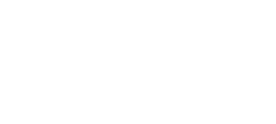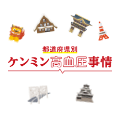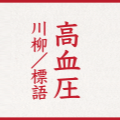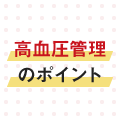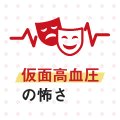芯が強く、昔かたぎの鹿児島県民
2018年(平成30年)は、明治維新から150周年の大きな節目の年です。鹿児島県民には、「近代日本を創ったのは薩摩」という自負があります。鹿児島県の県民性は、「ぼっけもん」という言葉で表現されることが多く、「大胆で豪快」、「芯が強い」といわれます。
私は6年前に大阪からこの地へ赴任してきたのですが、その前に鹿児島に関する歴史書や薩摩の偉人の伝記など、たくさん読みました。歴史を知ると、より県民性への理解が深まります。実際に私が鹿児島県民から感じることは、義理堅く、昔かたぎで曲がったことを嫌い、風習を大事にする、という保守的で頑固な気質です。また、明治維新ほどの歴史的大改革をやり遂げたことからも分かるように、自分たちの信念を貫く強い心とパワーを持っているのが鹿児島県民ですね。
鹿児島県民が持つ「てげてげ」という感覚
鹿児島県には28の有人離島があります。県本土と離島では県民性も違います。まず、言葉が全然違います。種子島や喜界島あたりになると、もう本土の人間でも全く言葉が分からないくらいです。鹿児島県民は基本的に大らかな人が多いのですが、南へ行けば行くほど、その大らかさは増していきます。「てげてげ」という言葉はご存知でしょうか?「適当」という意味の鹿児島の方言で、日常的にもよく使われる言葉です。この「てげてげでよかが(適当なところでいいよ)」という感覚は、鹿児島の大らかで心の広い県民性をよく表しています。

脳卒中発症の多さは、欧米化している
食生活と運動不足が原因か
県民の健康で気になるのが、「脳卒中」の多さです。鹿児島県民の脳卒中発症率の高さには、様々な原因が考えられます。鹿児島県民の食塩摂取量自体はそこまで多くはありません。それにもかかわらず、脳卒中の発症率が高いのは、「野菜・果物の摂取量の少なさ」に原因があるのではないかと考えています。野菜や果物には、体内の余分な塩分を体外に排泄してくれる「カリウム」という成分が多く含まれていますので、野菜や果物の摂取が少ないと体内の塩分が排泄されにくくなります。その結果、血圧が上昇し、脳卒中を引き起こす原因となってしまいます。また、魚を食べる習慣もあまりないですし、アルコール摂取量(主に焼酎)も多いですから、全体的に欧米に近い食事内容になってしまっているのでしょう。
もう一つの原因は、やはり「運動量の少なさ」だと思います。鹿児島は車社会なので、近くのスーパーに行くにも車を使います。自転車に乗る人が少ないために、スーパーに自転車置き場が設置されていないところもあるほどです。鹿児島には市電や路面電車などもありますが、都会ほど交通機関が細かく発達していませんし、バスも「1時間に1本しか来ない」という場所も多く、車移動が断然便利なのです。
鹿児島県の「脳卒中」を減らすには、「食生活の改善」と「運動不足の解消」という両面からのアプローチが必要ではないでしょうか。
ないかと考えています。野菜や果物には、体内の余分な塩分を体外に排泄してくれる「カリウム」という成分が多く含まれていますので、野菜や果物の摂取が少ないと体内の塩分が排泄されにくくなります。その結果、血圧が上昇し、脳卒中を引き起こす原因となってしまいます。また、魚を食べる習慣もあまりないですし、アルコール摂取量(主に焼酎)も多いですから、全体的に欧米に近い食事内容になってしまっているのでしょう。
もう一つの原因は、やはり「運動量の少なさ」だと思います。鹿児島は車社会なので、近くのスーパーに行くにも車を使います。自転車に乗る人が少ないために、スーパーに自転車置き場が設置されていないところもあるほどです。鹿児島には市電や路面電車などもありますが、都会ほど交通機関が細かく発達していませんし、バスも「1時間に1本しか来ない」という場所も多く、車移動が断然便利なのです。
鹿児島県の「脳卒中」を減らすには、「食生活の改善」と「運動不足の解消」という両面からのアプローチが必要ではないでしょうか。
「てげてげ」な県民性が健康を脅かしている!?
鹿児島県民の「てげてげ(適当)」感覚は、健康管理の上で大きな障壁になっています。たとえば、血圧管理に関していうと、高血圧についての知識も測定数値の管理も「てげてげ」なのです。上の血圧値(収縮期血圧)が160 mmHgと高かったとしても、「血圧が高いくらいで自分は健康そのもの」といった認識です。「血圧は下げなければいけないもの」という意識が乏しいのです。また、県内の田舎の方に行けば行くほど、家庭で血圧を測っている人は少なくなっていきます。昔がそうであったように、「血圧は病院で先生に測ってもらうもの」と今も変わらずに思っている方がかなり多いようです。
市民公開講座などで、健康に関して話す機会も多いのですが、「血圧を下げましょう」、「家で毎日血圧を測って健康管理をしましょう」と話しても、今までの認識を変えて行動に移してもらうのはなかなか難しいと感じています。今は、患者さんや一般の方に対しての発信だけでなく、若手医師や、医師以外の医療スタッフの教育にも力を入れて、最新かつ正しい情報の提供と、鹿児島県全体の健康意識の改革に取り組んでいます。意識の改革にはまだまだ時間がかかると思いますが、脳卒中の発症率は年々下がってきていますし、その効果は少しずつ出始めています。

「魚の塩漬けで焼酎を飲む」の特殊性に
気づこう
昔から続く生活習慣は、それが「普通」で「当たり前」のことだと思ってしまいがちです。しかし、健康面からみた場合、「悪しき習慣=特殊」であることが多いものです。たとえば、鹿児島県西部の海岸沿いには漁師町が多いのですが、ある地区では1人あたりの1日の食塩摂取量がいまだに20gを超えています。「魚の塩漬けで焼酎を飲む」という昔ながらの食習慣が「普通」のこととして現代でも続いているのです。そのほか、「焼酎は水より体にいい」と言って毎日たくさんお酒を飲むのも、近所のスーパーに当然のように車で行くのも、「当たり前(悪しき習慣)」です。
このように、食生活や運動習慣に問題があることをしっかり自覚することが大切です。健康のために「毎日血圧を測る」、「野菜・果物をたくさん食べる」、「たくさん歩く」という以前に、まずは自分たちの生活習慣の「特殊性」に気づくことが、健康への第一歩なのです。
いまだに20gを超えています。「魚の塩漬けで焼酎を飲む」という昔ながらの食習慣が「普通」のこととして現代でも続いているのです。そのほか、「焼酎は水より体にいい」と言って毎日たくさんお酒を飲むのも、近所のスーパーに当然のように車で行くのも、「当たり前(悪しき習慣)」です。
このように、食生活や運動習慣に問題があることをしっかり自覚することが大切です。健康のために「毎日血圧を測る」、「野菜・果物をたくさん食べる」、「たくさん歩く」という以前に、まずは自分たちの生活習慣の「特殊性」に気づくことが、健康への第一歩なのです。
垂水市の「健康づくり」を世界へ発信するプロジェクトがスタート
鹿児島県垂水市は、高齢化率(65歳以上人口)が40.3%という、県内でも高齢化の進行が著しい地域です。この高齢人口比率は2060年くらいの日本の姿だといわれています。現在、市の全面協力のもと、垂水市の65歳以上の方を対象にした予後調査研究(健康状態の経過を観察する研究)がスタートしています。この研究は、医師だけではなく、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、保険師、心理学、作業療法士、理学療法士など、多くの専門家がチームを組み、高齢者一人ひとりを長期にわたって徹底的に分析していこうというプロジェクトで、世界的にも類を見ない研究です。いわば、あらゆる方面からの健康サポートを通じて、「どれだけ住民を健康にできるか」が試されるプロジェクトです。
プロジェクトを通じて、高齢者の皆さんに血圧測定と筋力トレーニングを日常的に行っていただくことで、「脳卒中」や「心不全」の発症を減らすことができるのではないかと期待しています。また、高齢者が健康になることで、介護保険の支給額が減少することが予想され、「要介護者をどれだけ減らせるか」「地方財政をどれだけ救えるか」という点にも着目しています。
この取り組みによって、「元気で長生きできる高齢者が増えること」を願っています。垂水市自体の活力を取り戻すきっかけになれば、さらに良いですね。そして、この垂水市での取り組みをモデルケースとして、鹿児島県内のみならず全国に波及させていきたいと考えています。研究結果も世界へと積極的に発信していくつもりです。
「健康長寿」の取り組みを世界へ、垂水市での挑戦が始まっています。

田舎であることを
「言い訳」にしないでほしい
人口減少や高齢化が進む中、若者は地方の担い手として欠かせない存在ですが、いま、鹿児島県では若者の県外流出が問題になっています。若者に話を聞くと、「鹿児島は田舎だから」、「鹿児島は貧乏県だから(県民所得が全国45位)」という言葉をよく聞きます。「こんな田舎では何もできない、夢も持てない」と考える人が多いのかもしれません。しかし、夢を実現する過程に場所は関係ないはずです。与えられた場所、与えられたポジションで頑張れば、必ず最後には夢へ到達することができるのですから。
研究者の視点から見ると、鹿児島県ほどやりがいのある楽しい土地はなかなかないですよ。例えば、離島では人の出入りが少ない分、遺伝子も均質ですから、健診をしてデータを解析してみるとかなり面白い発見があるのではないかと思っています。先ほどご紹介した垂水市での調査研究しかり、ここでしかできない研究はたくさんあり、鹿児島県は研究者としての興味が尽きない場所です。
「与えられた場所でベストを尽くせば、結果は必ずついてくる」。これは私のモットーでもあります。鹿児島が田舎であることを嘆くのではなく、どこの場所にいたとしても、絶対に諦めない心があれば夢は必ず叶うのだと、私は信じています。
何もできない、夢も持てない」と考える人が多いのかもしれません。しかし、夢を実現する過程に場所は関係ないはずです。与えられた場所、与えられたポジションで頑張れば、必ず最後には夢へ到達することができるのですから。
研究者の視点から見ると、鹿児島県ほどやりがいのある楽しい土地はなかなかないですよ。例えば、離島では人の出入りが少ない分、遺伝子も均質ですから、健診をしてデータを解析してみるとかなり面白い発見があるのではないかと思っています。先ほどご紹介した垂水市での調査研究しかり、ここでしかできない研究はたくさんあり、鹿児島県は研究者としての興味が尽きない場所です。
「与えられた場所でベストを尽くせば、結果は必ずついてくる」。これは私のモットーでもあります。鹿児島が田舎であることを嘆くのではなく、どこの場所にいたとしても、絶対に諦めない心があれば夢は必ず叶うのだと、私は信じています。
おわりに ~県民の皆さんへ~
「てげてげ」は、愛すべき県民性ですが、健康に関しては「てげてげ」と言わずに、自分の生活習慣を見直してください。正しい知識のもと、日常生活でできることから少しずつ改善していけたらいいですね。まずは、近所のスーパーマーケットに車を使わず徒歩か自転車で行ってみることから始めてみませんか?
参考
厚生労働省「国民生活基礎調査」
厚生労働省「人口動態調査」
厚生労働省「患者調査」
厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況」
総務省統計局「家計調査」
総務省統計局 政府統計「e-Stat」
鹿児島県「脳卒中対策プロジェクト」
鹿児島県「健康かごしま21」