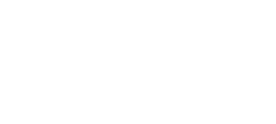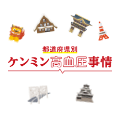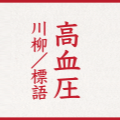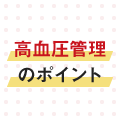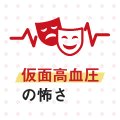高知県民にとって、お酒は日々の楽しみであり、コミュニケーション手段のひとつ
高知の県民性を表す土佐弁の言葉に、「いごっそう」、「はちきん」というものがあります。「いごっそう」は、負けず嫌いで頑固な高知県の男性を、「はちきん」は、活発で行動的な高知県の女性を表しています。いま活躍されている30~40歳代の方たちには、この言葉に表されるような気性を感じますね。
元気があって賑やかなことが好きなので、「よさこい祭り(毎年8月に開催される四国三大祭りの一つ)」は本当に盛り上がります。
もう一つ、高知を語る上でキーワードになるのは「お酒」です。酒豪が多い県といわれていますが、全くその通りで、皆さん本当にお酒が好きでよく飲まれます。全国統計と比較すると、1人当たりのお酒の消費量は2割ほど多いようです。高知県は四国の中でも山と海に囲まれているので、昔から他県との交流が少なく、生活の中にあまり楽しみがなかったのです。昔も今も「日々の楽しみはお酒」という人は多いですね。
「高知家(高知県はひとつの大家族)」という県のキャッチフレーズをご存知の方も多いと思います。このキャッチフレーズ通り、都会では失われつつある「人と人とのつながり」がいまだに色濃く残っているのが高知県です。高知県は田舎ですので、県民は「新しい人に出会うこと」をとても楽しみにしています。昔から新しい情報に飢えているので、「新しい人に出会って刺激を受け、情報を仕入れたい」という思いがあるのかもしれません。お酒が好きで、人とのコミュニケーションが好きな高知県民は、他県から来た方を家族のように受け入れる温かさを持っていますよ。

高知県の健康事情と「お酒」の問題
高知県は65歳以上の人口比率が32.85%で全国2位であり、高齢者の多い県です。若い方がどんどん都会に出て行ってしまい戻らないため、結果的に高齢者の数が増えているのでしょう。死亡率をみても、心臓疾患や肺炎などの高齢者で多くみられる病気の死亡率が高い傾向にあります。また、県民の健康面で気になるのが「歩数の少なさ」です(男女ともに全国ワースト)。
高知県だけではないと思いますが、日本の田舎では車がないと生活できません。公共の交通機関が少ないため、車に頼る生活になりがちで、どうしても歩数が少なくなくなってしまうのです。
県民の健康を支えるべく、高知県として取り組んでいることの一つは、やはり「お酒」についてです。毎日飲酒する人の割合が高く、20歳以上の県民1人当たり、年間約100リットルのアルコールを消費しているので、せめて全国平均の消費量程度に抑えたいところです。お酒は、「飲みすぎると健康に良くない」というだけでなく、飲酒運転、急性アルコール中毒、家庭内暴力、虐待、離婚、自殺など、様々なトラブルや社会問題を引き起こす原因にもなります。家族や周りの人への影響も大きいですね。そういった健康面以外の理由からも、いま、高知県ではお酒の消費量を減らそうという動きになっています。アルコールに対する健康教育や生活習慣改善の支援、相談拠点の設置など、様々な取り組みが始まっています。皆さんがうまくお酒と向き合い、自己調節ができるようになると、高知県の抱える健康問題や社会問題も改善されてくるのではないでしょうか。
医療施設、看護師数の多い高知県
都道府県別ランキングを見ると、高知県は「人口10万人当たりの病院数」で第1位です。なぜ高知県で医療施設が多いのか疑問の方も多いのではないでしょうか。これには高知の交通事情が深く関係しています。昔は本当に交通の便が悪かったため、地方に住んでいると、1回の診察のために何日もかけて来院する必要があったのです。場所によっては、大学病院で受診して帰宅するまでに4泊5日ほどの時間と労力を掛けないといけなかったのです。また、通院に不便な地方部では独居の高齢者も多く、病気を抱えていると家での療養が難しいため、病院が介護や療養のニーズの受け皿となる必要がありました。病院は、そういった方たちを引き受け、社会的な入院※を許していたため、結果的に高知県では病院数が多くなったのだと思います。今ではそういった事情での病院受け入れは許されなくなっていますし、他県と同様に入院期間は短くなり、病院もどんどん淘汰されていっています。
高知県は「人口10万人当たりの看護師数」でも全国1位ですね。高知県では、「男性が酒ばっかり飲んで働かないので女性が一生懸命働く」といわれています。女性が働く場合に、「看護師」という職業は、ある程度の収入が得られる仕事として魅力的なのかもしれません。高知県の女性は、本当にしっかりしていて働き者ですよ。
※入院による治療の必要性が低くなっていながら、帰る家がない、引き取り手がいない、家庭に介護者がいない、後遺症があるなどの理由で入院の続く状態。

「食塩摂取量」は低いが、低くない高血圧患者数
食事の面からみると、「食塩摂取量」は全国でもかなり低めです(1日の食塩摂取量:男性9.8g、女性8.4g)。しかし、高血圧の患者さんが特別少ないわけではありません。そこには、「運動の少なさ」や「飲酒量の多さ」などの食塩以外の要素が関係しているのではないかと考えています。
高血圧の患者さんには、「毎日家庭で血圧を測るように」とお願いしており、その家庭血圧値を基本に診療していますが、皆さん本当に毎日欠かさずよく測ってくれます。ただ、働き盛りの若い年代の方になると話は別で、それはなかなか難しいですね。日々の忙しい生活の中で、どうしても血圧測定を忘れてしまいがちになるのです。高血圧は、「苦しい」「痛い」などの苦痛を伴うわけではなく、自覚症状もありませんので、深刻さを持って治療に向き合っていただけないのでしょう。
高血圧の治療は、脳卒中や心臓疾患などの「高血圧が原因で将来起こりうる病気を予防するため」に必要なのです。例えるなら、「雨が降るかどうかわからないのに、毎日傘を持っていく」ようなものです。高知県だけでなく、全国の先生が同じように、働き盛りの若い患者さんの高血圧治療に頭を悩ませていると思います。治療の意味や必要性をわかっていただけるまで、何回も繰り返し、根気よく説明していくしかないですね。
社会インフラの整備で高知県の医療は大きく変わった
高知県のほとんどは山なので、海岸沿いの狭い地域に多くの人が住んでいます(高知市周辺に人口の約半分が集まっている)。アクセスの悪い地方部に住んでいるのはほとんどが高齢者です。昔は田舎に住んでいると、心筋梗塞や脳卒中といった「命に関わる緊急の病気」にかかった場合、病院までのアクセスが悪く、救急搬送に何時間もかかったため、命を落としてしまうケースがたくさんありました。しかし、今では高速道路が整備され、ヘリコプターを積極的に活用するようになったため、助かる命も増えています。病院に患者さんを運ぶのに何時間もかかっていたところが、20~30分程度で運べるようになったのですから。社会インフラが整備されたことで、高知県の医療は大きく改善されたと思います。

高知を見れば日本の将来が見えてくる
高知県は、全国に先行して高齢化が進んでいるといわれています。都市部に人口が集中し、地方部には高齢者が残る。そして、高齢単身世帯がどんどん増えていく。これは日本全国各地でみられる現象ですが、高知県ではその進行が顕著なのです。この高齢化の波は避けられません。かつてのような「病気になったら病院の世話になればいい」という時代は終わり、「自分の健康は自分で管理して守る」という時代に突入してきています。「お酒」についてもそうですが、高知県民の皆さんには、ご自身の生活習慣を今一度見直してみてほしいと思います。「家庭で血圧を測る」、「塩分を控える」、「運動する」。自分の健康のためにできることを、どれか1つでも良いので始めてみてください。日本人は真面目ですので、「すべてちゃんと取り組まなければ」と思いがちですが、少しずつで構わないのです。
まず何かを始めてみる。このことが、大切なのです。
という時代は終わり、「自分の健康は自分で管理して守る」という時代に突入してきています。「お酒」についてもそうですが、高知県民の皆さんには、ご自身の生活習慣を今一度見直してみてほしいと思います。「家庭で血圧を測る」、「塩分を控える」、「運動する」。自分の健康のためにできることを、どれか1つでも良いので始めてみてください。日本人は真面目ですので、「すべてちゃんと取り組まなければ」と思いがちですが、少しずつで構わないのです。
まず何かを始めてみる。このことが、大切なのです。
参考
厚生労働省「国民生活基礎調査」
厚生労働省「人口動態調査」
厚生労働省「患者調査」
厚生労働省「医療施設調査」
厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況」
高知県アルコール健康障害対策推進計画
川内 敦文「自治体担当者実情報告」:医療と社会 Vol.26 No.3 2016