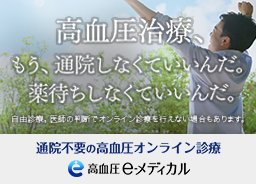vol.111 高い発見率で注目される、子宮頸がんの「HPV併用検診」
健康・医療トピックス
これまで大きな病気はしたことがない。健康には自信がある。こんな理由でがん検診を避けていませんか。医学の進歩でがんは早期発見、治療ができるようになり、約半数は治る時代になりました。しかし、日本では2人に1人ががんになり、年間約34万人ががんで亡くなっています。アメリカでは、がんによる死亡者が減っているのに日本では増えているその理由は、がん検診の受診率の低さにあるといわれています。
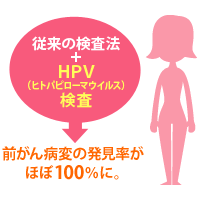
若い女性に増えている子宮頸がん
近年、20~30代の若い年代の女性に子宮頸がんが増えています。子宮頸がんの検診受診率を見てみるとアメリカは85.9%※1。一方、日本は24.5%※2 とかなり低いのが現状です。検診を受けないのは、実はがんが見つかったら怖いから。そんな声もよく聞かれます。しかし、子宮頸がんの検診は、がんになる前段階で発見できるメリットがあります。これは他の検診にはない大きな特長です。また、最近では「HPV(ヒトパピローマウイルス)併用検診」という検査によって、がんになる可能性のある細胞の発見率が高まっています。
子宮頸がんの原因
子宮頸がんの原因は、HPVの感染です。性的な接触によって女性が感染しますが、ほとんどの人は免疫の力で自然に治ります。ただし、約10%の人では半年以上の長期間にわたる持続感染が続きます。こうした場合に細胞の異形成が起こり、子宮頸がんに進行していくのです。HPVは100種類以上あり、このうちハイリスクと呼ばれるHPVは15種類。16型と18型が子宮頸がんから高頻度に検出されます。
HPVに感染しても症状はありませんが、出血などの症状が現れてからでは手術ができない状態まで、がんが進行していることが少なくありません。そのため、子宮頸がんの検診は非常に重要です。がんの最も初期の「上皮内(じょうひない)がん」や、がんになる前の「前(ぜん)がん病変」で発見できれば、治療は「円錐切除術(えんすいせつじょじゅつ)」という病変部の切除のみで済み、子宮を残すことができます。妊娠や分娩も可能で、生活の質を十分に保つことができるのです。
HPVに感染しても症状はありませんが、出血などの症状が現れてからでは手術ができない状態まで、がんが進行していることが少なくありません。そのため、子宮頸がんの検診は非常に重要です。がんの最も初期の「上皮内(じょうひない)がん」や、がんになる前の「前(ぜん)がん病変」で発見できれば、治療は「円錐切除術(えんすいせつじょじゅつ)」という病変部の切除のみで済み、子宮を残すことができます。妊娠や分娩も可能で、生活の質を十分に保つことができるのです。
2つの検査で高い発見率
検診では、へらやブラシなどの器具を使って子宮頸部の細胞をこすり取り、異常な細胞がないかを調べます。この方法での前がん病変の発見率は70~80%ですが、「HPV併用検診」では、発見率がほぼ100%に上昇します。「HPV併用検診」とは、従来の検査法にHPVに感染しているかを調べる「HPV検査」を加えたもの。細胞の異常とウイルス感染の検査を同時に行うことで発見率が高くなるため、異常がなければ検診の間隔もあけられます。アメリカでは5年に1回、オランダでは7年に1回の検診が勧められています。
現在、日本の子宮頸がんの定期検診は2年に1回、細胞の検査のみが行われていますが、約50市区町村では、すでにHPV検査を加えた併用検診を実施しており、今後、増えてくると予測されています。また、日本産婦人科医会では2つの検査を併用し、異常がなければ検診の間隔を3年に1回に延ばせるとしています。
現在、日本の子宮頸がんの定期検診は2年に1回、細胞の検査のみが行われていますが、約50市区町村では、すでにHPV検査を加えた併用検診を実施しており、今後、増えてくると予測されています。また、日本産婦人科医会では2つの検査を併用し、異常がなければ検診の間隔を3年に1回に延ばせるとしています。
ワクチンと検診で予防が可能
子宮頸がんは、予防できる唯一のがん。感染を防ぐワクチンが開発され、日本では中学1年生から高校1年生の女子を対象に、2010年から公費助成によるワクチン接種が行われています。子宮頸がんはワクチンだけで予防できると思われがちです。でも、それだけでは完璧ではありません。検診をプラスすることで子宮頸がんのリスクは減らせます。ワクチンを接種した女子は、20歳になったら定期検診を受けることが大事になります。
また、ワクチン接種は思春期女子の費用対効果(医療の費用と効果を見合わせた場合の評価)がよいとされていますが、大人の女性にも有効です。とくに若い女性の場合、まずは子宮頸がんの検診を受け、ワクチン接種を行うことは非常に効果的な子宮頸がんの予防となります。
また、ワクチン接種は思春期女子の費用対効果(医療の費用と効果を見合わせた場合の評価)がよいとされていますが、大人の女性にも有効です。とくに若い女性の場合、まずは子宮頸がんの検診を受け、ワクチン接種を行うことは非常に効果的な子宮頸がんの予防となります。
ワクチンの副反応を知っておこう
今年6月、厚生労働省が子宮頸がんのワクチン接種後の失神などについて医療機関に注意を呼びかけました。新聞などで記事を読んでワクチンは怖いと感じた人がいるのではないでしょうか。接種後の失神は、ワクチン自体が原因ではなく、多感な思春期の女子に起こりやすい「血管迷走神経反射(けっかんめいそうしんけいはんしゃ)」によるものです。注射を怖いと思い込む恐怖心や緊張がおもな原因です。また、ワクチンは筋肉に注射を打つため、人によっては筋肉痛が起きることがあります。接種の際には、このような副反応についても事前に理解して、過度に怖がらないことが重要。倒れてケガをしないように座るか、横になって受けましょう。ワクチン接種が安心して受けられるように周囲にいる人が緊張をほぐすなどの配慮を行なうことも大切です。
監修 自治医科大学附属さいたま医療センター 産科婦人科 教授 今野 良先生
出典 ※1、※2 OECD Health Data 2011
監修 自治医科大学附属さいたま医療センター 産科婦人科 教授 今野 良先生
出典 ※1、※2 OECD Health Data 2011
※このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。