vol.115 食べる機能を支える口腔リハビリテーション
健康・医療トピックス
2012年10月、東京都小金井市に口腔リハビリテーションを専門に行う「日本歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック」が開設されました。
「口腔リハビリテーション」は、口腔ケアや機能トレーニングによって、食べる機能の回復を支援するというもの。病気やその後遺症、高齢などで食べる機能に障害が生じた人が対象で、歯科の中でも特殊な分野です。同クリニックでは外来や訪問診療のほかに、医療・介護専門職向けの研修会や一般向けの介護食の講習会なども開催し、食べる障害に対しての理解を深めてもらおうと啓発活動にも取り組んでいます。口腔リハビリテーションという言葉はまだ聞きなれませんが、高齢者の誤嚥(ごえん)や窒息事故などが増えていることから、今後、注目のキーワードになりそうです。
「口腔リハビリテーション」は、口腔ケアや機能トレーニングによって、食べる機能の回復を支援するというもの。病気やその後遺症、高齢などで食べる機能に障害が生じた人が対象で、歯科の中でも特殊な分野です。同クリニックでは外来や訪問診療のほかに、医療・介護専門職向けの研修会や一般向けの介護食の講習会なども開催し、食べる障害に対しての理解を深めてもらおうと啓発活動にも取り組んでいます。口腔リハビリテーションという言葉はまだ聞きなれませんが、高齢者の誤嚥(ごえん)や窒息事故などが増えていることから、今後、注目のキーワードになりそうです。
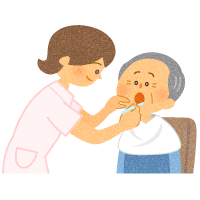
窒息事故の約半数は食べ物が原因
年末年始のニュースでよく見聞きするのは、餅による高齢者の窒息事故です。この時期になると特に多いように思われますが、食べ物による窒息事故は一年中起きています。厚生労働省の平成22年人口動態統計によると、不慮の窒息で死亡した人は9879人。交通事故で死亡する人よりも、窒息事故で亡くなる人のほうが多いのです。このうち、食べ物の誤嚥による気道閉塞で亡くなった人は、4869人。食べ物による窒息事故が約半数を占めています。餅による窒息事故が起こると、餅が悪いと簡単に決めてしまいがちです。しかし、「自分の食べる機能と食べ物が合っているのか?は大きな問題点。食べる本人(または食べさせる人)がこれらを認識する、これが口腔リハビリテーションの視点です。
体の衰えとともに低下する「食べる機能」
食べることは、実は誰でも簡単にできることではありません。ふつうに食べられるようになるには、体の発達と合わせて、五感(視覚・聴覚・ 味覚・嗅覚・触覚)から受け取る情報など、周囲の環境からの刺激によって“食べたい気持ち”になることが必要です。成長過程にある子どもでは、体の発達に障害があったり、外部からの刺激がなかったりするとうまく食べられません。
高齢者では病気の影響によって、食べる機能に障害が起こることが多くなります。たとえば、認知症、脳梗塞、パーキンソン病などです。これらの病気で体が思うように動かなくなると、口の中やのどから胃の間にある食べ物や空気の通り道の機能も低下。食べたり、飲み込んだりすることが不自由になるのです。
また、病気になっていなくても、高齢になると体の衰えとともに食べる機能も低下していきます。いくつになっても、たとえ寝たきりになったとしても、自由に好きなものが食べたい。食べさせてあげたい。多くの人はそう望みますが、なかなか思い通りにはいかないものなのです。
食べ物は口の中で咀嚼された後、のどから「ごっくん」と飲み込んで食道に入ります。このごっくんの機能が低下すると、飲み込んだつもりでも食べ物がのどに残ってしまったり、気管や肺に誤って入って誤嚥性肺炎を起こしたりします。食べる機能の低下で起こる障害は、低栄養になって痩せることだけではないのです。食べた物が空気の通り道を塞ぐと息ができなくなり、命にかかわるということもきちんと理解しておくことが大切です。
高齢者では病気の影響によって、食べる機能に障害が起こることが多くなります。たとえば、認知症、脳梗塞、パーキンソン病などです。これらの病気で体が思うように動かなくなると、口の中やのどから胃の間にある食べ物や空気の通り道の機能も低下。食べたり、飲み込んだりすることが不自由になるのです。
また、病気になっていなくても、高齢になると体の衰えとともに食べる機能も低下していきます。いくつになっても、たとえ寝たきりになったとしても、自由に好きなものが食べたい。食べさせてあげたい。多くの人はそう望みますが、なかなか思い通りにはいかないものなのです。
食べ物は口の中で咀嚼された後、のどから「ごっくん」と飲み込んで食道に入ります。このごっくんの機能が低下すると、飲み込んだつもりでも食べ物がのどに残ってしまったり、気管や肺に誤って入って誤嚥性肺炎を起こしたりします。食べる機能の低下で起こる障害は、低栄養になって痩せることだけではないのです。食べた物が空気の通り道を塞ぐと息ができなくなり、命にかかわるということもきちんと理解しておくことが大切です。
楽しい食事、会話、歌のある生活を送ろう
では、食べる機能を低下させないためには、どうしたらいいのでしょうか。年を重ねつつ、機能を維持するには、普段から外交的な生活を心がけることです。口は息をして、食べるためだけの器官ではありません。人と会話をしたり、歌ったりして楽しむこともできるのです。食べたり、おしゃべりしたりすることは、人とかかわること。食事がおいしいと感じるのは、一緒に食べる人がいるからです。そのため、食事が楽しみになるような生活を送ることが大切。家族や友人とおしゃべりしたり、カラオケで歌ったりする環境があると、食べる機能を維持する大きな力になります。
食べる機能の状態を調べるには、食事時間もひとつの目安になります。純粋に食事をしている時間だけで30分以上かかっているようなら、なんらかの問題が考えられます。たとえば、食事の形態が合っていない、食事に集中できない、食事中に寝てしまう…などです。在宅介護の現場では、食事に1時間以上かかるケースが見られます。このような状態が続くと、食事から能率よく栄養がとれず、低栄養につながります。食事に時間がかかる場合は、料理がその人にとって食べやすい大きさ、形、硬さになっているのか、また一口の量が多くなっていないか、食べるときの姿勢はよいかなど、周囲の人はよく見守ってあげましょう。
また、噛むことは脳のよい刺激になるといわれています。ただし、硬いものをがんばって噛むことがいいのかというとそうではありません。自分の噛む能力に合った食べ物を選ぶことが一番大切です。
監修 日本歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック 院長 菊谷 武先生
食べる機能の状態を調べるには、食事時間もひとつの目安になります。純粋に食事をしている時間だけで30分以上かかっているようなら、なんらかの問題が考えられます。たとえば、食事の形態が合っていない、食事に集中できない、食事中に寝てしまう…などです。在宅介護の現場では、食事に1時間以上かかるケースが見られます。このような状態が続くと、食事から能率よく栄養がとれず、低栄養につながります。食事に時間がかかる場合は、料理がその人にとって食べやすい大きさ、形、硬さになっているのか、また一口の量が多くなっていないか、食べるときの姿勢はよいかなど、周囲の人はよく見守ってあげましょう。
また、噛むことは脳のよい刺激になるといわれています。ただし、硬いものをがんばって噛むことがいいのかというとそうではありません。自分の噛む能力に合った食べ物を選ぶことが一番大切です。
監修 日本歯科大学 口腔リハビリテーション多摩クリニック 院長 菊谷 武先生
※このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。














