vol.117 科学の目で心と体を研究 期待される「認知行動療法」
健康・医療トピックス
気持ちが前向きで幸せを感じるとき、体や健康にはどのような影響があるのか―。それを科学的な立場から研究していこうと2012年9月、精神科の医師が中心になって「日本ポジティブサイコロジー医学会」が発足しました。
病気が回復していく過程では、その人の体力のほかにプラスの精神力も必要といわれています。海外では、心のあり方に焦点を当てた「ポジティブ精神医学」が注目され、心と体の関連について研究が行われています。現在、日本ではうつ病などの精神疾患が増え続けており、厚生労働省の平成23年患者調査によると、傷病分類別の入院患者で最も多いのは「精神及び行動の障害」で282万3千人。次いで「循環器系の疾患」251万3千人、「新生物(がん)」150万6千人の順となっています。いまや心の病気が循環器(高血圧性疾患、心疾患、脳血管疾患)やがんの患者を上回る状況です。同学会では、病気との関連以外にストレスを感じたとき、バランスよく現実に目を向けながら考えを切り替えて心の力を引き出す「認知行動療法」の取り組みが重要と考え、予防も視野に入れて、基礎から社会面まで含めた研究で実証していきたいとしています。
病気が回復していく過程では、その人の体力のほかにプラスの精神力も必要といわれています。海外では、心のあり方に焦点を当てた「ポジティブ精神医学」が注目され、心と体の関連について研究が行われています。現在、日本ではうつ病などの精神疾患が増え続けており、厚生労働省の平成23年患者調査によると、傷病分類別の入院患者で最も多いのは「精神及び行動の障害」で282万3千人。次いで「循環器系の疾患」251万3千人、「新生物(がん)」150万6千人の順となっています。いまや心の病気が循環器(高血圧性疾患、心疾患、脳血管疾患)やがんの患者を上回る状況です。同学会では、病気との関連以外にストレスを感じたとき、バランスよく現実に目を向けながら考えを切り替えて心の力を引き出す「認知行動療法」の取り組みが重要と考え、予防も視野に入れて、基礎から社会面まで含めた研究で実証していきたいとしています。
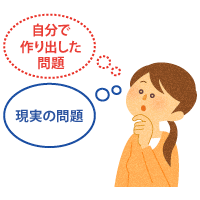
効果や活用が注目される認知行動療法
「病は気から」の言葉通り、不安やつらい気持ちが強くなると病気にかかりやすくなることがわかっています。心が自律神経に影響し、免疫力の低下やホルモンのバランスが乱れて、風邪などの感染症や心筋梗塞を起こしやすくなります。また、病気や災害などで一命をとりとめても、落ち込みやうつ病の状態が続くと死亡率が高いといわれています。
心から始まる悪循環を回避するには、安定した気持ちを取り戻すことが大切。その治療法として、いま期待されているのが認知行動療法です。物事の受け取り方や考え方を見直して、とらえ方や行動を現実に則した内容に調整していくもので、東日本大震災の被災地、宮城県女川町では、地域住民の心の健康を支える活動として行われています。もともとはアメリカでうつ病の治療法として始まりましたが、その他の精神疾患や精神的なストレスの対処法としても有効とされ、効果や活用が注目されています。
心から始まる悪循環を回避するには、安定した気持ちを取り戻すことが大切。その治療法として、いま期待されているのが認知行動療法です。物事の受け取り方や考え方を見直して、とらえ方や行動を現実に則した内容に調整していくもので、東日本大震災の被災地、宮城県女川町では、地域住民の心の健康を支える活動として行われています。もともとはアメリカでうつ病の治療法として始まりましたが、その他の精神疾患や精神的なストレスの対処法としても有効とされ、効果や活用が注目されています。
心がピンチに陥ったときの対処法
認知行動療法は、バランスよく現実に目を向けながら考えを切り替えて心の力を引き出す方法です。知っていれば、自分だけでなく、悩んでいる人に寄り添うこともできますので、対処法のポイントをご紹介しましょう。
学校や職場での人間関係、病気、災害、失業、大切な人を失ったとき……。心がこのような危機的な状況に直面すると、私たちの行動は「ファイト」「フライト」「フリーズ」の3つに分かれます。ファイトは前向きに闘う。フライトは逃げる。フリーズは固まって動けない状態。つまり、どうしたらいいかわからなくなっているということです。
フライトやフリーズに陥ったら、すぐに前向きな気持ちにはなれません。そんなときは、自分らしく生きるために気持ちの軌道修正をしてみましょう。「1.孤立しない」「2.何が大事か確認する」「3.現実の問題と作り出した問題を仕分けする」の3つが重要なステップです。
たとえば、仕事で失敗したとき。つらかったら、一人で悩みを抱え込まないで誰かに相談し、助けてもらいましょう。孤立しないことが重要です。次に、自分にとって何が大切かを考えてみましょう。悩んでいるときには、うまくいかなかったすべてが大事に思えて、後悔ばかりしてしまいます。本当は何がしたかったのか。大切に思っていたことが見えなくなっているのです。「もうダメだ」「どうせダメだ」と考えると、ここで考えはストップし、物事は先に進みません。「現実の問題と自分で作り出した問題を仕分ける」ことが大事です。仕事で失敗したのは現実の問題。でも、“どうせダメだ”は、自分で作り出した想像の問題です。このように仕分けることで大事なことが見えてきます。そして「やってみないとわからない」というように考え方も切り替わります。現実を見ながら行動することで、気持ちが前向きになっていくのです。
人が幸せを感じる原動力は、人のためになる、役に立つということです。人の助けを借りるということは相手に迷惑がかかりそうですが、適度に手助けしてもらうことは、助ける人の心も幸せにします。お互いの気持ちにとって意味があることです。
また、やる気はじっと待っていても起こらないので、自分の好きなこと、気持ちが晴れることに積極的に取り組んでみましょう。コツは、難しくないことを一つずつクリアしていくこと。「できた」「やってよかった」という実感があると、意欲が湧いてやる気が出てきます。詳しくは、認知療法活用サイト『こころのスキルアップ・トレーニング』を参照してください。
監修 国立精神・神経医療研究センター
認知行動療法センター センター長 大野 裕先生
学校や職場での人間関係、病気、災害、失業、大切な人を失ったとき……。心がこのような危機的な状況に直面すると、私たちの行動は「ファイト」「フライト」「フリーズ」の3つに分かれます。ファイトは前向きに闘う。フライトは逃げる。フリーズは固まって動けない状態。つまり、どうしたらいいかわからなくなっているということです。
フライトやフリーズに陥ったら、すぐに前向きな気持ちにはなれません。そんなときは、自分らしく生きるために気持ちの軌道修正をしてみましょう。「1.孤立しない」「2.何が大事か確認する」「3.現実の問題と作り出した問題を仕分けする」の3つが重要なステップです。
たとえば、仕事で失敗したとき。つらかったら、一人で悩みを抱え込まないで誰かに相談し、助けてもらいましょう。孤立しないことが重要です。次に、自分にとって何が大切かを考えてみましょう。悩んでいるときには、うまくいかなかったすべてが大事に思えて、後悔ばかりしてしまいます。本当は何がしたかったのか。大切に思っていたことが見えなくなっているのです。「もうダメだ」「どうせダメだ」と考えると、ここで考えはストップし、物事は先に進みません。「現実の問題と自分で作り出した問題を仕分ける」ことが大事です。仕事で失敗したのは現実の問題。でも、“どうせダメだ”は、自分で作り出した想像の問題です。このように仕分けることで大事なことが見えてきます。そして「やってみないとわからない」というように考え方も切り替わります。現実を見ながら行動することで、気持ちが前向きになっていくのです。
人が幸せを感じる原動力は、人のためになる、役に立つということです。人の助けを借りるということは相手に迷惑がかかりそうですが、適度に手助けしてもらうことは、助ける人の心も幸せにします。お互いの気持ちにとって意味があることです。
また、やる気はじっと待っていても起こらないので、自分の好きなこと、気持ちが晴れることに積極的に取り組んでみましょう。コツは、難しくないことを一つずつクリアしていくこと。「できた」「やってよかった」という実感があると、意欲が湧いてやる気が出てきます。詳しくは、認知療法活用サイト『こころのスキルアップ・トレーニング』を参照してください。
監修 国立精神・神経医療研究センター
認知行動療法センター センター長 大野 裕先生
※このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。














