vol.120 手術とともに進化!早期回復を支える「栄養療法」
健康・医療トピックス
最新の医療機器の登場、手術方法や手技の向上などによって、進歩し続ける外科治療。困難とされた病気の治療が可能になり、患者の身体への負担も軽減され、入院日数も短くなっています。外科治療というと手術ばかりに関心が集まりがちですが、その進歩とともに患者の命を支えてきたのが「栄養療法」です。たとえば、食道がんは、手術法の進歩と栄養療法の確立によって安全に治療できるようになった病気のひとつ。また、最近では入院患者の栄養管理を行う「栄養サポートチーム」(NST)の普及が進み、広がりつつあります。2010年には診療報酬に「栄養サポートチーム加算」が収載され、1500以上の医療機関がNSTの稼働施設に登録されています。
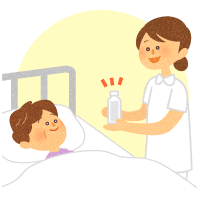
静脈から始まった栄養療法
日本でNSTが始まったのは2001年頃から。医療の現場では、それ以前から栄養療法の重要性が認識されていました。食道、胃、大腸などとくに消化器の疾患では、病状や術後の状態によっては食べられず、消耗する患者が多かったためです。このような栄養障害を改善する大きな一歩となったのが、1960年代の後半から1970年代の初めに登場した「完全静脈栄養法」。中心静脈カテーテルから点滴だけで、体に必要な栄養素をすべて入れるという方法です。
1990年代になると「腸」の重要性が指摘され始めます。腸の働きは消化吸収と排出だけではありません。免疫細胞が多く存在する最大の免疫臓器である腸は、異物や外敵から体を守る生体防御の最前線です。腸の中にはたくさんの細菌や毒素があり、腸のバリア機能が低下すると腸壁を通って、それらが体の中に侵入します。口から食べたり、腸管から栄養を入れたりして腸を使うと、腸管のバリア機能が高まり、それらの侵入を阻止する力が高まります。同時に全身の感染防御の機能が高まります。さらに、傷の治りも早く、全身の炎症反応も抑えられることがわかってきたのです。
その後、2000年頃から「免疫栄養」という栄養療法が広がり始めます。栄養素の中には、薬のような用い方で免疫機能や傷の治りを改善するものがあります。それらを強化した栄養剤の内服によって、術後の感染症を減らそうという治療法です。
診療現場でこうした栄養療法を適切に行うことで術後の合併症が減少し、入院日数の短縮や医療費の削減にもつながるということがだんだんに知られるようになり、日本でNSTの取り組みが広がってきています。
1990年代になると「腸」の重要性が指摘され始めます。腸の働きは消化吸収と排出だけではありません。免疫細胞が多く存在する最大の免疫臓器である腸は、異物や外敵から体を守る生体防御の最前線です。腸の中にはたくさんの細菌や毒素があり、腸のバリア機能が低下すると腸壁を通って、それらが体の中に侵入します。口から食べたり、腸管から栄養を入れたりして腸を使うと、腸管のバリア機能が高まり、それらの侵入を阻止する力が高まります。同時に全身の感染防御の機能が高まります。さらに、傷の治りも早く、全身の炎症反応も抑えられることがわかってきたのです。
その後、2000年頃から「免疫栄養」という栄養療法が広がり始めます。栄養素の中には、薬のような用い方で免疫機能や傷の治りを改善するものがあります。それらを強化した栄養剤の内服によって、術後の感染症を減らそうという治療法です。
診療現場でこうした栄養療法を適切に行うことで術後の合併症が減少し、入院日数の短縮や医療費の削減にもつながるということがだんだんに知られるようになり、日本でNSTの取り組みが広がってきています。
いま注目の術前の栄養管理
ところで、一昔前まで手術前は飲食を絶って腸は空っぽにした方がいいといわれてきましたが、現在は変わってきています。手術の前日に「これを飲んでください」と看護師さんから飲み物などを勧められた経験がある方もいるのではないでしょうか。
これは、医療の現場で新しい流れになっている「ERAS(イーラス)」と呼ばれる患者管理のプログラムです。手術の前夜と当日の朝、糖を含んだ補水液などを摂取します。術後の早期回復を目指してヨーロッパで始まった考え方で、手術前後の絶食期間を短縮して、早期から口で食べることを勧めるものです。水分を補うことで脱水による過剰な点滴が減り、腸がむくみにくくなり、早期から食べられるようになります。さらに、術後の血糖値の上昇を防ぐメリットもあります。術後の血糖値の大きな乱れや筋肉の崩壊もある程度、抑えることがわかっています。
これは、医療の現場で新しい流れになっている「ERAS(イーラス)」と呼ばれる患者管理のプログラムです。手術の前夜と当日の朝、糖を含んだ補水液などを摂取します。術後の早期回復を目指してヨーロッパで始まった考え方で、手術前後の絶食期間を短縮して、早期から口で食べることを勧めるものです。水分を補うことで脱水による過剰な点滴が減り、腸がむくみにくくなり、早期から食べられるようになります。さらに、術後の血糖値の上昇を防ぐメリットもあります。術後の血糖値の大きな乱れや筋肉の崩壊もある程度、抑えることがわかっています。
腸に働きかける「シンバイオティクス療法」
腸に注目した栄養療法では、「シンバイオティクス療法」も期待されています。シンバイオティクスとは、プレバイオティクス(腸内で善玉菌の餌となる食物繊維など)と、プロバイオティクス(人体に有益な効果をもたらす細菌)の両方を投与する方法です。
腸内に棲む細菌と私たちは、共生関係にあります。元気なときは、食事に含まれる食物繊維などを餌にして腸内細菌が短鎖脂肪酸を作ります。これが腸管の細胞のエネルギー源になり、善玉菌が優位になっています。ところが、ストレスがかかると腸内細菌の力関係は、ダイナミックに変化します。病原性のある細菌が爆発的に増えてバランスが崩れるのです。この治療法は、手術前後に乳酸菌製剤や乳酸菌飲料、食物繊維などを一緒に摂取し、腸内環境を正常化して術後の感染症などを防ぐ効果が期待されています。
腸内に棲む細菌と私たちは、共生関係にあります。元気なときは、食事に含まれる食物繊維などを餌にして腸内細菌が短鎖脂肪酸を作ります。これが腸管の細胞のエネルギー源になり、善玉菌が優位になっています。ところが、ストレスがかかると腸内細菌の力関係は、ダイナミックに変化します。病原性のある細菌が爆発的に増えてバランスが崩れるのです。この治療法は、手術前後に乳酸菌製剤や乳酸菌飲料、食物繊維などを一緒に摂取し、腸内環境を正常化して術後の感染症などを防ぐ効果が期待されています。
栄養療法の注意点
栄養状態を保つことは、すべての病気治療の基本です。栄養療法はとても重要で効果も期待されていますが、注意点もあります。たとえば、「免疫栄養」を行うと術後の感染症が減少すると報告されています。しかし、重症疾患の患者では炎症が強くなって臓器障害が起き、かえって悪化するという報告もされています。このため、適切な使い分けが大事とされ、免疫増強ばかりでなく、免疫調整タイプの栄養剤も用いられています。
このように、栄養療法はどのような病態、手術、ストレスがあるかによって、選択される治療法が異なります。病状が複雑な患者ほど注意が必要で、今後ますます研究が進んでいく分野です。
監修 東京大学医学部附属病院 手術部 准教授 深柄和彦先生
このように、栄養療法はどのような病態、手術、ストレスがあるかによって、選択される治療法が異なります。病状が複雑な患者ほど注意が必要で、今後ますます研究が進んでいく分野です。
監修 東京大学医学部附属病院 手術部 准教授 深柄和彦先生
※このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。














