vol.22 適切な治療を受けていないCOPD患者
健康・医療トピックス
COPDとはChronic(慢性)Obstructive(閉塞性)Pulmonary(肺)Disease(疾患)の略です。この慢性閉塞性肺疾患に悩む人は多く、厚生労働省発表の患者統計では約20万人にも上ります。しかも、順天堂大学医学部の福地義之助教授らの疫学調査によると、約530万人もの潜在患者がいるというのです。
COPDはかつて『慢性気管支炎』や『肺気腫』と呼ばれていましたが、2001年にWHO(世界保健機関)によって名称の統一がなされ、診療ガイドラインも示されました。
COPDは肺へ酸素を取り入れて不要な二酸化炭素を排出するガス交換が十分にできなくなる疾患です。ガス交換は肺の末端のぶどうの房のような形をした肺胞で行われていますが、その肺胞間の壁が壊れて酸素を十分に取り入れられなくなるのです。同時に、気管支の炎症をも合併しています。
患者は50~70代の人に集中しており、「息切れ」「咳」「痰」といった症状があり、特に重い荷物を持ったり、階段を上ったりして負担をかけたときに息切れが起きます。重症化すると自宅での酸素吸入を余儀なくされ、さらに、中等度以上では肺がんの合併症のある方が20%にも達し、肺がんとの関連性も取りざたされています。
COPDの主な原因は喫煙です。喫煙習慣のある人の15%以上にCOPDの中等度以上の症状がみられます。喫煙以外の原因としては、「職業的有害物質吸入」「大気汚染」などがあります。
ここで問題なのは、きちっとした治療を受けていない患者が実に多いということです。COPDの専門医たちは、「息切れといった症状を患者さんが訴えても、年のせい!ですまされてしまっている」とか、「風邪と診断されている」といったケースも多いと指摘しています。
COPDで一度壊れた肺胞は元に戻ることはありません。早期発見・早期治療を行い、悪化をくいとめることが重要となります。そうすれば酸素吸入に至ることなく、QOL(クオリティ・オブ・ライフ = 生活の質)を低下させずに普通の生活を続けることができます。だからこそその症状に気付いたら、ぜひCOPDの専門医に正確に診断していただくことが大切なのです。
診断は肺機能検査(スパイロメトリー)で肺の換気能力を調べるほか、胸のX線やCT検査を行って判断します。
COPD治療の基本は、(1)「禁煙」に始まり(喫煙者の場合)、次いで(2)「薬物療法」。これは気管支拡張薬である抗コリン薬やβ2(ベータツー)刺激薬の吸入薬を使います。昨年12月には新薬の抗コリン薬チオトロピュームも登場しました。そして、(3)「栄養指導」。体型別に栄養の摂取指導をおこない、呼吸効率改善をおこないます。(4)「運動」。息切れしない体力を維持するための運動をおこないます。(5)「呼吸理学療法」。呼吸リハビリテーションで呼吸機能を最大限に生かす訓練をします。さらに重症のCOPDと判明した場合は、「酸素療法」になります。
COPDはかつて『慢性気管支炎』や『肺気腫』と呼ばれていましたが、2001年にWHO(世界保健機関)によって名称の統一がなされ、診療ガイドラインも示されました。
COPDは肺へ酸素を取り入れて不要な二酸化炭素を排出するガス交換が十分にできなくなる疾患です。ガス交換は肺の末端のぶどうの房のような形をした肺胞で行われていますが、その肺胞間の壁が壊れて酸素を十分に取り入れられなくなるのです。同時に、気管支の炎症をも合併しています。
患者は50~70代の人に集中しており、「息切れ」「咳」「痰」といった症状があり、特に重い荷物を持ったり、階段を上ったりして負担をかけたときに息切れが起きます。重症化すると自宅での酸素吸入を余儀なくされ、さらに、中等度以上では肺がんの合併症のある方が20%にも達し、肺がんとの関連性も取りざたされています。
COPDの主な原因は喫煙です。喫煙習慣のある人の15%以上にCOPDの中等度以上の症状がみられます。喫煙以外の原因としては、「職業的有害物質吸入」「大気汚染」などがあります。
ここで問題なのは、きちっとした治療を受けていない患者が実に多いということです。COPDの専門医たちは、「息切れといった症状を患者さんが訴えても、年のせい!ですまされてしまっている」とか、「風邪と診断されている」といったケースも多いと指摘しています。
COPDで一度壊れた肺胞は元に戻ることはありません。早期発見・早期治療を行い、悪化をくいとめることが重要となります。そうすれば酸素吸入に至ることなく、QOL(クオリティ・オブ・ライフ = 生活の質)を低下させずに普通の生活を続けることができます。だからこそその症状に気付いたら、ぜひCOPDの専門医に正確に診断していただくことが大切なのです。
診断は肺機能検査(スパイロメトリー)で肺の換気能力を調べるほか、胸のX線やCT検査を行って判断します。
COPD治療の基本は、(1)「禁煙」に始まり(喫煙者の場合)、次いで(2)「薬物療法」。これは気管支拡張薬である抗コリン薬やβ2(ベータツー)刺激薬の吸入薬を使います。昨年12月には新薬の抗コリン薬チオトロピュームも登場しました。そして、(3)「栄養指導」。体型別に栄養の摂取指導をおこない、呼吸効率改善をおこないます。(4)「運動」。息切れしない体力を維持するための運動をおこないます。(5)「呼吸理学療法」。呼吸リハビリテーションで呼吸機能を最大限に生かす訓練をします。さらに重症のCOPDと判明した場合は、「酸素療法」になります。
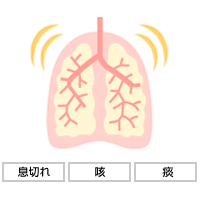
※このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。
執筆者プロフィール

松井 宏夫
医学ジャーナリスト
- 略歴
- 1951年生まれ。
医療最前線の社会的問題に取り組み、高い評価を受けている。
名医本のパイオニアであるとともに、分かりやすい医療解説でも定評がある。
テレビは出演すると共に、『最終警告!たけしの本当は怖い家庭の医学』(テレビ朝日)に協力、『ブロードキャスター』(TBS)医療企画担当・出演、『これが世界のスーパードクター』(TBS)監修など。
ラジオは『笑顔でおは天!!』のコーナー『松井宏夫の健康百科』(文化放送)に出演のほか、新聞、週刊誌など幅広く活躍し、NPO日本医学ジャーナリスト協会副理事長を務めている。
主な著書は『全国名医・病院徹底ガイド』『この病気にこの名医PART1・2・3』『ガンにならない人の法則』(主婦と生活社)、『高くても受けたい最新の検査ガイド-最先端の検査ができる病院・クリニック47』(楽書ブックス)など著書は35冊を超える。














