vol.34 帯状疱疹後神経痛のリスクを下げる
健康・医療トピックス
帯状疱疹(たいじょうほうしん)に悩まされる人は毎年、人口10万人当たり300~500人に上ります。帯状疱疹の出るところによっては、顔面神経麻痺を引き起こしたり、耳の聞こえを悪くしたりもしますが、それ以上に、対応が遅れると“辛い痛み”に数年も悩まされる『帯状疱疹後神経痛』になることもあります。帯状疱疹を帯状疱疹後神経痛にしないためには――。
帯状疱疹は子どものころにかかった水痘ウイルス、つまり水ぼうそうのウイルスの再活性化によって起こる病気です。
免疫力が低下した状態になると、神経痛のような痛みが生じ、その痛みが出て4~5日後に出てくる赤みがかった水疱が特徴です。皮膚の症状や痛みは、普通そのうちに自然治癒しますが、皮膚の症状が消えた後にもしばらくして痛みが出る場合があります。これを帯状疱疹後神経痛といいます。
帯状疱疹が治っても約10%の人は、3カ月くらいして出てくる帯状疱疹後神経痛に悩まされる可能性があります。短い人は数カ月で痛みから解放されますが、長い人は3~5年、10年近くも悩まされている人もいます。
帯状疱疹後神経痛は帯状疱疹の重症度に応じて起こるものではなく、患者さんによって異なるため、早期発見・早期治療が極めて重要なポイントとなります。
ですから、痛みの後に赤みがかった水疱が出てきたら、遅くとも3日以内に治療を開始するのが、帯状疱疹後神経痛のリスクを低下させてくれることにつながります。
帯状疱疹の治療は薬物療法で、塩酸バラシクロビル(商品名:バルトレックス)という抗ウイルス薬の経口薬がよく使われています。これを1日3回(8時間おきに)、1週間服用するとともに抗菌外用薬を使って、皮膚の水疱やただれを悪化させないようにします。
そのほか、帯状疱疹の出る場所によっては、「不眠」「便秘」などが合併します。そのときは睡眠薬、下剤で対応します。顔面に出てきたときは、早くから皮膚科だけでなく眼科や耳鼻咽喉科と協力体制をとって、共同で治療が行われます。
経口薬が良くなったとはいっても、やはりより効果の高い治療法は抗ウイルス薬の点滴静注(静脈注射)です。この場合は入院が必要となります。しかし、入院は1週間程度ですむので、より重症で高齢の人は入院施設のある病院で診察を受け、入院治療で回復を目指すのが、その後の神経痛のリスクを下げるにはもっとも効果的と考えられています。どちらにしても、帯状疱疹は免疫力の低下が原因なので、あせらずじっくりと休養をとって体力の回復を心がけましょう。
帯状疱疹は子どものころにかかった水痘ウイルス、つまり水ぼうそうのウイルスの再活性化によって起こる病気です。
免疫力が低下した状態になると、神経痛のような痛みが生じ、その痛みが出て4~5日後に出てくる赤みがかった水疱が特徴です。皮膚の症状や痛みは、普通そのうちに自然治癒しますが、皮膚の症状が消えた後にもしばらくして痛みが出る場合があります。これを帯状疱疹後神経痛といいます。
帯状疱疹が治っても約10%の人は、3カ月くらいして出てくる帯状疱疹後神経痛に悩まされる可能性があります。短い人は数カ月で痛みから解放されますが、長い人は3~5年、10年近くも悩まされている人もいます。
帯状疱疹後神経痛は帯状疱疹の重症度に応じて起こるものではなく、患者さんによって異なるため、早期発見・早期治療が極めて重要なポイントとなります。
ですから、痛みの後に赤みがかった水疱が出てきたら、遅くとも3日以内に治療を開始するのが、帯状疱疹後神経痛のリスクを低下させてくれることにつながります。
帯状疱疹の治療は薬物療法で、塩酸バラシクロビル(商品名:バルトレックス)という抗ウイルス薬の経口薬がよく使われています。これを1日3回(8時間おきに)、1週間服用するとともに抗菌外用薬を使って、皮膚の水疱やただれを悪化させないようにします。
そのほか、帯状疱疹の出る場所によっては、「不眠」「便秘」などが合併します。そのときは睡眠薬、下剤で対応します。顔面に出てきたときは、早くから皮膚科だけでなく眼科や耳鼻咽喉科と協力体制をとって、共同で治療が行われます。
経口薬が良くなったとはいっても、やはりより効果の高い治療法は抗ウイルス薬の点滴静注(静脈注射)です。この場合は入院が必要となります。しかし、入院は1週間程度ですむので、より重症で高齢の人は入院施設のある病院で診察を受け、入院治療で回復を目指すのが、その後の神経痛のリスクを下げるにはもっとも効果的と考えられています。どちらにしても、帯状疱疹は免疫力の低下が原因なので、あせらずじっくりと休養をとって体力の回復を心がけましょう。
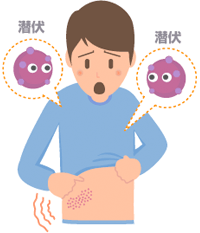
※このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。
執筆者プロフィール

松井 宏夫
医学ジャーナリスト
- 略歴
- 1951年生まれ。
医療最前線の社会的問題に取り組み、高い評価を受けている。
名医本のパイオニアであるとともに、分かりやすい医療解説でも定評がある。
テレビは出演すると共に、『最終警告!たけしの本当は怖い家庭の医学』(テレビ朝日)に協力、『ブロードキャスター』(TBS)医療企画担当・出演、『これが世界のスーパードクター』(TBS)監修など。
ラジオは『笑顔でおは天!!』のコーナー『松井宏夫の健康百科』(文化放送)に出演のほか、新聞、週刊誌など幅広く活躍し、NPO日本医学ジャーナリスト協会副理事長を務めている。
主な著書は『全国名医・病院徹底ガイド』『この病気にこの名医PART1・2・3』『ガンにならない人の法則』(主婦と生活社)、『高くても受けたい最新の検査ガイド-最先端の検査ができる病院・クリニック47』(楽書ブックス)など著書は35冊を超える。














