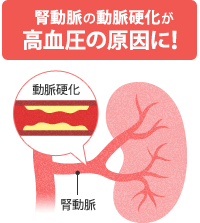腎動脈狭窄症になると、なぜ血圧が高くなるのでしょうか。
腎臓の細胞からは、血圧調節に関係するレニンという酵素が分泌されています。腎動脈が狭くなり、腎臓への血液の流入量が減少すると、それに反応してレニンの分泌量が増え、血圧を上昇させるホルモン(アンジオテンシンⅠ、Ⅱ)が活性化されます(※2)。これは本来、腎臓への血流量を増やし、腎機能を維持するための生体防御システムなのですが、その半面、高血圧を招くことになります。
腎動脈狭窄症は気づきにくいため、発見が遅れ、あるときから急速に高血圧になる人が少なくありません。また高血圧の治療中でも、一部の降圧薬にはレニン・アンジオテンシン系の働きを抑え、その結果、腎機能を低下させるものがあります。この場合には高血圧の悪化に加え、心不全などのリスクも高くなるので、降圧薬を服用中に尿の変化(にごり、量など)、むくみなどの症状が出たら、早めに医師に伝えて検査を受けることが大切です(※3)。
腎動脈狭窄症が発見された場合、治療法は大別すると薬による方法とステント(金属製のチューブ)による手術があります。狭窄の程度が軽く、また進行がゆるやかな場合には、医師の判断により薬で血圧をコントロールしつつ、狭窄の進行を抑える治療もおこなわれます。
一方、根本的な治療としては、腎動脈の狭窄部にカテーテルでステントを入れ、血管を拡張する方法が主流となっています。ステントは以前と比較すると改良が進み、合併症などのリスクも少なくなっていますが、医師の話をよく聞いておくようにしましょう。
(※2)レニンの分泌量が増えると、血圧上昇にかかわるアンジオテンシンⅠが活性化され、続いてより強い作用をもつアンジオテンシンⅡができることで、血圧が急上昇することが判明しています。
(※3)糖尿病などほかの病気の併発でも、腎機能の障害が起こるので、症状や対処法などには個人差があります。