
オムロンの血圧計
血圧が気になったら家庭で血圧測定
家庭で簡単に正確に測定するための機能が充実
詳しくはこちら →(別ウィンドウで開く)
(※1)脳卒中とは、脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞の総称です。
(※2)脳内出血やくも膜下出血については、男女とも糖尿病との関連は認められませんでした。厚生労働省「多目的コホート研究」による、40歳~69歳の男女約3.6万人を対象とした調査研究。同調査では、空腹時血糖値126mg/dl以上、随時血糖値200mg/dl以上の人、及び糖尿病治療中の人を糖尿病群と規定。
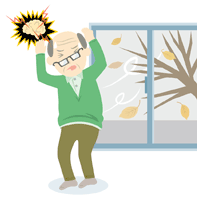
このうち、ラクナ脳梗塞は日本人に多くみられ、主な原因は高血圧とされています。それに対して、アテローム性脳梗塞は欧米人に多く、高血圧や脂質異常症、糖尿病による動脈硬化が原因とされています。また塞栓性脳梗塞は、不整脈の1つである心房細動により、心臓に血栓ができることが原因として指摘されています。
このように脳梗塞は、タイプによって原因などが少しずつ違うとされています。しかし糖尿病との関連については、厚生労働省研究班の調査によると、「糖尿病があると、いずれのタイプの脳梗塞も発症リスクが高くなる」のです。
血糖値が正常な人の発症リスクを1とした場合、男性ではラクナ脳梗塞(2.04)、アテローム性脳梗塞(1.94)、塞栓性脳梗塞(2.85)。女性ではラクナ脳梗塞(3.85)、アテローム性脳梗塞(4.64)、塞栓性脳梗塞(4.24)と、いずれも高いリスクを示しています(※4)。
日本人に多いラクナ脳梗塞は、脳の細い血管に生じる小さな梗塞のため、発作などの大きな症状が起こりにくいのが特徴です。症状がほとんど出ないこともあるため、「隠れ脳梗塞」とも呼ばれています。
一方、突然の大きな発作になりやすいアテローム性脳梗塞や塞栓性脳梗塞も、食生活の洋風化などによって日本人に増えつつあります(塞栓性脳梗塞は、長嶋茂雄・巨人軍名誉監督がなったことでも知られています)。したがって糖尿病の改善や予防は、すべての脳梗塞の予防につながる重要な対策の1つだといえるでしょう。
(※3)ラクナ脳梗塞とアテローム性脳梗塞を「脳血栓症」、塞栓性脳梗塞を「脳塞栓症」と、2つに分けて呼ぶこともあります。
(※4)男女を合わせると、全脳梗塞では2.65、ラクナ脳梗塞で2.65、アテローム性脳梗塞で2.58、塞栓性脳梗塞で3.32となります。
糖尿病の改善にはもう1つ、適度の運動が大切です。
中高年になると、加齢や運動不足、肥満などによって、インスリンの働きが悪化しがちです。運動をすると、骨格筋での糖の利用が増え、インスリン感受性が改善される(インスリン受容体の働きが良くなる)ことで、血糖値が低下します。また、肥満が解消されることも、血糖値の改善につながります。糖尿病の方はもちろんですが、予備軍の方も定期的な運動を生活のなかに取り入れるようにしましょう。
従来、血糖値の改善には有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)が効果的とされてきましたが、近年の研究から筋力トレーニングにも同様の効果があることが分かっています。自分がやりやすい運動を1回30分程度、週3日~4日を目安に続けましょう(筋トレの効果については、「はじめよう!ヘルシーライフ」Vol.114「家庭での『筋トレ』で血糖値を改善」ご参照ください)。
ただし、インスリンなどの薬物治療を受けている場合、運動をするタイミングによっては低血糖を起こすことがあります。原則として食事前の運動はよくありませんが、薬の量を調整する方法もあるので、かならず医師に相談してから運動をするようにしてください。
(※5)「糖尿病食事療法のための食品交換表」(日本糖尿病学会)は、日常的に食べている食品を栄養素別に分類し、80kcal相当の分量(g)を1単位として紹介したもの。たとえば、医師の指示により1日の摂取カロリーが1600kcalとされている場合、各栄養素グループから食べたいものをバランス良く選びながら、合計で20単位になるようにする。
中高年の方には、睡眠中にトイレに立つことを嫌って、夜間には水分を制限するケースがよくみられます。しかし、水分をきちんと摂らないと血液の流れが低下し、固まりやすくなります。脳梗塞の予防のために、就寝前に軽く水分補給をしましょう。水を入れた小さなペットボトル(倒れてもこぼれにくい)を枕元に置いておき、トイレに起きたときや朝起きたときなどに少しずつ飲むのもいい方法です(ただし、心臓病や腎臓病などで治療を受けている方は、医師の指示に従ってください)。
夜間にトイレに行くときは、カーディガンなどを1枚はおる、スリッパをはくなどして、寒さ対策を心がけましょう。
また、朝起きたあと、急いで行動したり、すぐに運動を始めたりすると、血圧が急激に上昇します。起床直後はからだをゆっくり動かすことを心がけ、朝のトイレではいきまないこと。運動をする場合は準備運動を入念にし、からだを温めてから始めましょう。
一方、予防のためには、脳梗塞の軽いサインを見逃さないことも大切です。ラクナ脳梗塞のような小さな梗塞では、早朝や朝起きたときなどに「なんとなく、からだのどこかがおかしい」と感じることがあります。多くの場合、片方の手足のしびれや脱力感、足のもつれ、言葉がうまく出ないなどの症状ですが、はっきり分からなくても「どこかおかしい」と感じたら要注意。放置せずに、早めに受診して検査を受けましょう。
もしも急に倒れるような脳梗塞の発作が起きた場合は、早急な治療が必要です。脳の血管がふさがり、酸素や栄養が届かなくなると、すぐに脳細胞がダメージを受け始めます。治療が早いほど命の危険が少なく、後遺障害も軽度で済むので、周囲の人も協力して、ためらわずに救急車を呼んでください。
※このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。