vol.11 糖尿病の指導は「食後過血糖」にも広がる
健康・医療トピックス
現在、わが国の糖尿病患者は予備軍も含めると、1620万人ともいわれています。そして、このまま増え続けると2010年には2200万人を超えると予測され、5人に1人が糖尿病患者もしくは予備軍ということになります。
糖尿病とは血糖値が正常値を超えて異常に高くなる状態をいいます。私たちが食事でとる栄養素のひとつである糖質は、小腸で消化されブドウ糖という形になって吸収されます。そして、肝臓を介して全身へ運ばれ、大切なエネルギー源となります。このときに増加した血糖を筋肉や脂肪組織に取り込むように作用するのが、すい臓から分泌されるインスリンです。血糖はこのインスリンによってコントロールされています。
ところが、重要なインスリンが不足したり、十分に分泌されていても効き具合が悪かったりすると、血糖値はあまり下がらず高血糖状態が続き、糖尿病になります。
糖尿病の本当の恐ろしさは、高血糖が長く続いた結果起こる慢性合併症です。その合併症は、大きく「細小血管障害」と「大血管障害」の2つに分類されます。細小血管障害には糖尿病網膜症、腎症、神経障害などがあり、大血管障害には脳梗塞、心筋梗塞、下肢閉塞性動脈硬化症(組織が死んで腐敗してしまう下肢の壊疽(えそ)に結びつく)などがあります。
糖尿病患者で高血糖が長く続くと当然、両方を合併します。しかし、予備軍といわれる人々の中でも、食後の血糖値が高い「食後過血糖」の人は、糖尿病患者と同じくらい大血管障害を起こしやすいことが多くの臨床報告からわかってきました。
糖尿病と食後過血糖の違いは、血糖値で分かれます。この場合は「ブドウ糖負荷試験2時間値」をみます。正常型は140mg/dl未満、境界型は140mg/dl以上~200mg/dl未満、糖尿病型は200mg/dl以上です。
食後過血糖といわれるのは境界型でも血糖値が170mg/dl以上の人です。これに該当する人のうち60~70%の人が3年以内に糖尿病に移行することもわかっています。それだけに、境界型と指摘された人は、食後血糖値を半年に1回は調べるようにし、積極的に食事療法、運動療法に取り組むようにしましょう。
食事療法は、糖尿病の人と同じです。糖質(50~60%)、脂質(20~25%)、たんぱく質(15~25%)をバランスよく摂取し、適正なエネルギー量をとるようにしましょう。
運動療法は、食後1時間頃に運動することが大事です。血糖値が最も上昇する食後1時間から1時間30分くらいに運動すると血液中のブドウ糖が消費されやすいことから、気軽に出来るウォーキングなどを、20分から30分程度行いましょう。
糖尿病とは血糖値が正常値を超えて異常に高くなる状態をいいます。私たちが食事でとる栄養素のひとつである糖質は、小腸で消化されブドウ糖という形になって吸収されます。そして、肝臓を介して全身へ運ばれ、大切なエネルギー源となります。このときに増加した血糖を筋肉や脂肪組織に取り込むように作用するのが、すい臓から分泌されるインスリンです。血糖はこのインスリンによってコントロールされています。
ところが、重要なインスリンが不足したり、十分に分泌されていても効き具合が悪かったりすると、血糖値はあまり下がらず高血糖状態が続き、糖尿病になります。
糖尿病の本当の恐ろしさは、高血糖が長く続いた結果起こる慢性合併症です。その合併症は、大きく「細小血管障害」と「大血管障害」の2つに分類されます。細小血管障害には糖尿病網膜症、腎症、神経障害などがあり、大血管障害には脳梗塞、心筋梗塞、下肢閉塞性動脈硬化症(組織が死んで腐敗してしまう下肢の壊疽(えそ)に結びつく)などがあります。
糖尿病患者で高血糖が長く続くと当然、両方を合併します。しかし、予備軍といわれる人々の中でも、食後の血糖値が高い「食後過血糖」の人は、糖尿病患者と同じくらい大血管障害を起こしやすいことが多くの臨床報告からわかってきました。
糖尿病と食後過血糖の違いは、血糖値で分かれます。この場合は「ブドウ糖負荷試験2時間値」をみます。正常型は140mg/dl未満、境界型は140mg/dl以上~200mg/dl未満、糖尿病型は200mg/dl以上です。
食後過血糖といわれるのは境界型でも血糖値が170mg/dl以上の人です。これに該当する人のうち60~70%の人が3年以内に糖尿病に移行することもわかっています。それだけに、境界型と指摘された人は、食後血糖値を半年に1回は調べるようにし、積極的に食事療法、運動療法に取り組むようにしましょう。
食事療法は、糖尿病の人と同じです。糖質(50~60%)、脂質(20~25%)、たんぱく質(15~25%)をバランスよく摂取し、適正なエネルギー量をとるようにしましょう。
運動療法は、食後1時間頃に運動することが大事です。血糖値が最も上昇する食後1時間から1時間30分くらいに運動すると血液中のブドウ糖が消費されやすいことから、気軽に出来るウォーキングなどを、20分から30分程度行いましょう。
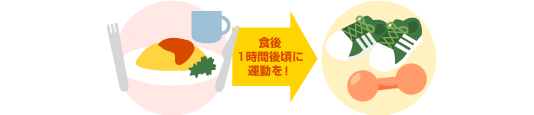

※このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。
執筆者プロフィール

松井 宏夫
医学ジャーナリスト
- 略歴
- 1951年生まれ。
医療最前線の社会的問題に取り組み、高い評価を受けている。
名医本のパイオニアであるとともに、分かりやすい医療解説でも定評がある。
テレビは出演すると共に、『最終警告!たけしの本当は怖い家庭の医学』(テレビ朝日)に協力、『ブロードキャスター』(TBS)医療企画担当・出演、『これが世界のスーパードクター』(TBS)監修など。
ラジオは『笑顔でおは天!!』のコーナー『松井宏夫の健康百科』(文化放送)に出演のほか、新聞、週刊誌など幅広く活躍し、NPO日本医学ジャーナリスト協会副理事長を務めている。
主な著書は『全国名医・病院徹底ガイド』『この病気にこの名医PART1・2・3』『ガンにならない人の法則』(主婦と生活社)、『高くても受けたい最新の検査ガイド-最先端の検査ができる病院・クリニック47』(楽書ブックス)など著書は35冊を超える。














