
オムロンの血圧計
血圧が気になったら家庭で血圧測定
家庭で簡単に正確に測定するための機能が充実
詳しくはこちら →(別ウィンドウで開く)
日本人の死因の第4位である『脳卒中(脳血管疾患)』。その脳卒中は大きく「脳出血」と「脳梗塞」に分けられます。1975年までは脳出血患者が多かったのですが、それ以降、脳梗塞患者が増え、今日では脳卒中の約60%が脳梗塞で占められています。
これまで脳梗塞は「一命をとりとめても深刻な後遺症をもたらす」病気でしたが、最近では早期治療を行うことで、より少ない後遺症でとどめられるようになってきました。脳梗塞を発症してから治療を受けるまでの時間が短いほど、後遺症をもたらすリスクが軽減します。小さなサインを見逃さず、できるだけ早く医療機関を受診することが大切です。
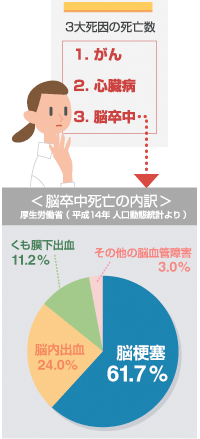
最近では、救急で運び込まれた医療機関で脳梗塞の診断をするときに、3つのタイプに分けて診断するようになりました。脳梗塞の治療は、その種類によって異なるからです。発症したらできるだけ早い段階で、脳梗塞の原因を調べて、タイプに応じた治療をすることが求められます。
(1) 心原性脳梗塞症
心房細動、リウマチ性心臓病(弁膜症)、心筋梗塞、心筋症といった心臓病が原因で、心臓にできた血栓が血流に乗って脳に流れていき、脳の血管を詰まらせてしまうものです。
(2) ラクナ梗塞
ラクナとは「小さなくぼみ」の意味。高血圧が主な原因で、脳の細かい血管が損傷を受けて詰まることで起こる脳梗塞です。日本人に多いタイプとされています。
(3) アテローム血栓性脳梗塞
コレステロールが酸化して血管壁に入り込み、血管内におかゆのようなドロドロした固まりが溜まって血管の内側が狭くなり、血管が詰まって発症する脳梗塞です。高血圧や糖尿病が引き金となって、動脈硬化が進むことで起こります。
*抗凝固薬・・・血が固まるのを抑制する薬
*抗血小板薬・・・血を固まりにくくする薬
このほかに、2001年からは脳細胞に悪影響を及ぼす活性酸素を除去する脳保護薬(フリーラジカルスカベンジャー)を用いた治療も行われており、早期治療の成果をより高めています。早期にこれらの治療を行い、発病から3時間以内に血流が再開できるか否かが、その後の状態を大きく左右します。
近年では、脳梗塞を含む脳卒中のサインを見逃さないための「ACT-FAST(アクト・ファスト)キャンペーン活動」が展開されており、その成果もあってか、後遺症の少ない患者さんも増えてきました。気になる異変があったら、早めに医療機関を受診しましょう。
(参考)
『脳梗塞の治療』大塚製薬
https://www.otsuka.co.jp/health-and-illness/stroke/treatments-for-cerebral-infarction/
『[103] 脳梗塞が起こったら』循環器病情報サービス
http://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/pamphlet/brain/pamph103.html
『平成30年(2018) 人口動態統計月報年計(概数)の概況』厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai18/dl/gaikyou30.pdf
更新日:2021.05.07
※このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。