vol.62 気を付けたいドライブ時の健康管理
はじめよう!
ヘルシーライフ
ヘルシーライフ
睡眠不足と居眠り運転
旅行や帰省などで、長距離ドライブをすることが多くなる季節です。
安全運転のためには、日ごろの健康管理が欠かせませんが、それを怠った典型ともいえるのが「居眠り運転」です。運転中に眠くなったという経験は、ほとんどのドライバーにあるでしょう。高速道路を時速80kmで走行している場合、わずか3秒間の居眠りで約70mも進むため、大事故につながりかねません。 近年、居眠り運転の原因の一つとして重視されているのが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。SASになると、睡眠中に何度も呼吸が止まるため、脳や体が休まらず、日中に強い眠気におそわれます。運転中でも我慢できずに眠ってしまったり、起きていても集中力が欠け、漫然運転(周囲に注意を払わないぼんやり運転)をするなどの症状がみられ、非常に危険な状態になります。
睡眠中に大いびきをかくなど、SASの兆候がみられる人は、きちんと検査を受けておくことが大切です(SASの詳細については、「はじめよう!ヘルシーライフ」Vol.18をご参照ください)。
またSASほどでなくても、普段睡眠不足だと、居眠り運転をしやすい傾向がみられます。厚生労働省の調査では、普段の睡眠時間が5時間未満の人は、5時間以上眠っている人と比べると、「居眠り運転」が3倍以上も多く、事故の一歩手前の「ヒヤリハット体験」も2.5倍になることが報告されています(※1)。
旅行などに出かける前は、仕事をあわただしく片付け、睡眠不足のままで出掛けることが少なくありません。旅行中も慣れないホテルのベッドなどが原因で、よく眠れないこともあります。
こうした場合には、自分が睡眠不足気味であることを自覚し、サービスエリアや道の駅などで早めに休憩をとったり、出発前にガムを買うなど、自分なりの眠気防止の対策を準備しておくことが大切です。運転中によく眠くなるという人は、薬局でカフェイン入りのドリンク剤を買っておくといいでしょう。
安全運転のためには、日ごろの健康管理が欠かせませんが、それを怠った典型ともいえるのが「居眠り運転」です。運転中に眠くなったという経験は、ほとんどのドライバーにあるでしょう。高速道路を時速80kmで走行している場合、わずか3秒間の居眠りで約70mも進むため、大事故につながりかねません。 近年、居眠り運転の原因の一つとして重視されているのが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。SASになると、睡眠中に何度も呼吸が止まるため、脳や体が休まらず、日中に強い眠気におそわれます。運転中でも我慢できずに眠ってしまったり、起きていても集中力が欠け、漫然運転(周囲に注意を払わないぼんやり運転)をするなどの症状がみられ、非常に危険な状態になります。
睡眠中に大いびきをかくなど、SASの兆候がみられる人は、きちんと検査を受けておくことが大切です(SASの詳細については、「はじめよう!ヘルシーライフ」Vol.18をご参照ください)。
またSASほどでなくても、普段睡眠不足だと、居眠り運転をしやすい傾向がみられます。厚生労働省の調査では、普段の睡眠時間が5時間未満の人は、5時間以上眠っている人と比べると、「居眠り運転」が3倍以上も多く、事故の一歩手前の「ヒヤリハット体験」も2.5倍になることが報告されています(※1)。
旅行などに出かける前は、仕事をあわただしく片付け、睡眠不足のままで出掛けることが少なくありません。旅行中も慣れないホテルのベッドなどが原因で、よく眠れないこともあります。
こうした場合には、自分が睡眠不足気味であることを自覚し、サービスエリアや道の駅などで早めに休憩をとったり、出発前にガムを買うなど、自分なりの眠気防止の対策を準備しておくことが大切です。運転中によく眠くなるという人は、薬局でカフェイン入りのドリンク剤を買っておくといいでしょう。
(※1)厚生労働省による、トラック運転手を対象とした2006年度調査(2008年発表)。睡眠時間5時間未満の運転手を1とした場合、睡眠時間5時間以上の運転手の居眠り運転は0.3、ヒヤリハット体験は0.43になります。

-
居眠り運転による事故が特に多い時間帯は、(1)深夜から早朝、(2)午後2~4時です。私たちの体には、24時間周期、12時間周期などの睡眠リズムがあり、ちょうどその時間帯に当たるためです。深夜の運転はできるだけさける、午後は15分程度仮眠をとるなどの方法で、居眠り運転を防止しましょう。
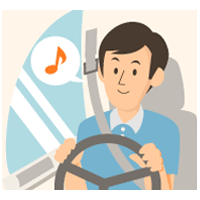
運転で血圧が急速に上がる
運転そのものが、私たちの健康に影響を及ぼすこともあります。その典型が、ストレスです。
ハンドルを握ると誰でも少し緊張しますが、そのときに血圧がかなり上がることを知っていますか。
運転中の血圧の変化については、まだ大規模な調査はありませんが、例えば時速30~40km程度の安全運転時でも、平均すると最高血圧が25mmHg上がり、時速60~80kmでスラローム運転をすると、最高血圧が平均で43mmHgも上昇するという報告がみられます(※2)。
主な原因は緊張からくるストレスですが、日ごろから高血圧の人はもちろん、正常血圧の人でも運転時には高血圧状態になりやすくなることがわかります。それだけ脳卒中や心筋梗塞のリスクも高くなります。
特に高速道路での運転や、無理な追い越しなどの乱暴な運転は、血圧上昇の原因になりやすいので注意が必要です。
別の調査では、運転開始から100分程度までは、走行環境に適応するために脈拍などの心身機能が高まりやすいことも分かっています(※3)。
また、運転中は神経が過敏になり、日ごろおとなしい人でも怒りやすい精神状態になっています。よその車の割り込みや追い越しに、すぐカッとなるドライバーは少なくありませんが、怒りも血圧を急上昇させる原因の一つです。
こうしたことから、血圧が高めの人や緊張をしやすい人などは、次のことを心掛けましょう。
(1) 日ごろの血圧管理をしっかりしておく。
(2) ドライブ中は早めに休憩をとり、体の緊張をほぐしたり、トイレに行くなどして、ストレス解消をする。
(3) 自分に過度のストレスを掛ける危険な運転(スピードの出し過ぎや無理な追い越しなど)をしない。
(4) よその車に対しては「譲る」気持ちを持って、ゆとりある運転をする。
ハンドルを握ると誰でも少し緊張しますが、そのときに血圧がかなり上がることを知っていますか。
運転中の血圧の変化については、まだ大規模な調査はありませんが、例えば時速30~40km程度の安全運転時でも、平均すると最高血圧が25mmHg上がり、時速60~80kmでスラローム運転をすると、最高血圧が平均で43mmHgも上昇するという報告がみられます(※2)。
主な原因は緊張からくるストレスですが、日ごろから高血圧の人はもちろん、正常血圧の人でも運転時には高血圧状態になりやすくなることがわかります。それだけ脳卒中や心筋梗塞のリスクも高くなります。
特に高速道路での運転や、無理な追い越しなどの乱暴な運転は、血圧上昇の原因になりやすいので注意が必要です。
別の調査では、運転開始から100分程度までは、走行環境に適応するために脈拍などの心身機能が高まりやすいことも分かっています(※3)。
また、運転中は神経が過敏になり、日ごろおとなしい人でも怒りやすい精神状態になっています。よその車の割り込みや追い越しに、すぐカッとなるドライバーは少なくありませんが、怒りも血圧を急上昇させる原因の一つです。
こうしたことから、血圧が高めの人や緊張をしやすい人などは、次のことを心掛けましょう。
(1) 日ごろの血圧管理をしっかりしておく。
(2) ドライブ中は早めに休憩をとり、体の緊張をほぐしたり、トイレに行くなどして、ストレス解消をする。
(3) 自分に過度のストレスを掛ける危険な運転(スピードの出し過ぎや無理な追い越しなど)をしない。
(4) よその車に対しては「譲る」気持ちを持って、ゆとりある運転をする。
(※2)埼玉県警察本部交通企画課と(社)日本交通科学協議会・小川昌子医師らによる実験。25~77歳の健康な人20人を対象に、2回に分け、安全運転時やスラローム運転時などの血圧や脈拍を測定したもの。
(※3)芝浦工業大学・岩倉成志教授らによる、運転中の脈拍(心拍のR波とR波の間隔の変化)などを測定した実験(土木学会第56回年次学術講演会)。
運転後にも注意を
心臓発作などの危険性は、運転中だけでなく、運転直後にもみられます。
ドイツの健康研究機関が「心臓発作を起こす1時間前に何をしていたか」について調査したところ、車の運転をしていたという人が、ほかの場所にいた人の3倍もいたことを報告しています。特に渋滞など混んだ道路にいた人が多く、また、運転していなくても、車やバスに乗っていたという人も多くみられました。
そのためドイツの報告では、「汚染物質の多い排気ガスを吸い続けることが、心臓発作の引きがねになりやすい」としています。そして、運転後1時間程度は注意するように、と警告しています(※4)。
排気ガスだけが直接の原因かどうかは解明されていませんが、一つの可能性として、渋滞時などに窓を開けっぱなしにして排気ガスを長時間吸うのは、やめたほうがいいでしょう。
一方、日本でも、運転後に心臓発作を起こす例が多いことが指摘されています。その原因とされるのは、排気ガスではなくストレスです。特に日ごろから仕事や人間関係で慢性的ストレスがたまっていたり、過労状態にあると、運転がきっかけとなり、運転後の心臓発作などのリスクが高まると推測されています。
こうしたことから、ドライブの前にはストレスや疲れをためないように心掛けることも大切です。
ドイツの健康研究機関が「心臓発作を起こす1時間前に何をしていたか」について調査したところ、車の運転をしていたという人が、ほかの場所にいた人の3倍もいたことを報告しています。特に渋滞など混んだ道路にいた人が多く、また、運転していなくても、車やバスに乗っていたという人も多くみられました。
そのためドイツの報告では、「汚染物質の多い排気ガスを吸い続けることが、心臓発作の引きがねになりやすい」としています。そして、運転後1時間程度は注意するように、と警告しています(※4)。
排気ガスだけが直接の原因かどうかは解明されていませんが、一つの可能性として、渋滞時などに窓を開けっぱなしにして排気ガスを長時間吸うのは、やめたほうがいいでしょう。
一方、日本でも、運転後に心臓発作を起こす例が多いことが指摘されています。その原因とされるのは、排気ガスではなくストレスです。特に日ごろから仕事や人間関係で慢性的ストレスがたまっていたり、過労状態にあると、運転がきっかけとなり、運転後の心臓発作などのリスクが高まると推測されています。
こうしたことから、ドライブの前にはストレスや疲れをためないように心掛けることも大切です。
(※4)ドイツのGFS環境健康研究センターの調査(2004年)

-
ドライブ中にはBGMを聴く人も多いでしょう。実はBGMの選曲も、安全運転に大きな影響があります。イギリスの自動車関連の調査機関(RACファウンデーション)の調査では、ドライブ時に最も危険な曲はワーグナーの「ワルキューレの騎行」とされています。同調査によると、ハイテンポの曲を大きな音量で聴くほど、心臓の動悸(どうき)が速く、血圧も高くなるため、危険回避の動作が遅くなることが指摘されています。
※このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。














