
オムロンの血圧計
血圧が気になったら家庭で血圧測定
家庭で簡単に正確に測定するための機能が充実
詳しくはこちら →(別ウィンドウで開く)
(※1)腎臓の機能が悪化した状態を「腎不全」といいますが、その予備軍までを含めて「慢性腎臓病」といいます。従来の糖尿病性腎症や慢性糸球体腎炎なども、総称して現在は「慢性腎臓病」とされています。
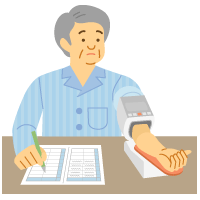
130mmHg(収縮期血圧)/80mmHg(拡張期血圧)未満
(ただし尿中たんぱく量が1日1g以上の場合は、125/75mmHg未満)
日本腎臓学会・日本高血圧学会「CKD診療ガイド(高血圧編)」より
この目標からわかるように、通常の高血圧治療の場合よりも少し厳しい数値が定められています。とくに尿中たんぱく量が多いと、慢性腎臓病が悪化しやすいため、より厳しい血圧コントロールが求められます。
実際の治療では、症状の程度に応じて医師の判断により、薬物治療や生活指導(食生活改善、禁煙など)がおこなわれますが、治療効果の確認には家庭での血圧測定が重要になってきます。
家庭での血圧測定は、通常朝晩2回おこないますが、最近の研究から、とくに朝の収縮期血圧が慢性腎臓病の参考になりやすいことがわかってきています。慢性腎臓病の患者さんを対象とした調査によると、朝の収縮期血圧が「130mmHg以上」と「130mmHg未満」のグループを比較した場合、後者のグループのほうが腎臓機能の低下率が明確に低いという報告がみられます(※3)。つまり、朝の収縮期血圧を130mmHg未満にコントロールできると、慢性腎臓病の改善効果がみられ、腎臓の働きがよくなるわけです。
日常の予防においても、こうした数値などを目安にして、毎日の血圧チェックをしましょう。慢性腎臓病の予防は、心血管疾患の予防にもつながるので、きちんと血圧コントロールに取り組むことが大切です。
なお、尿たんぱくが出ているかどうかは、市販の尿試験紙でも調べることができます。ただし、正確な数値まではわからないので、自己判断で一喜一憂せず、気になる場合は早めに受診してください。
(※2)尿検査では主に尿たんぱくの量を、血液検査では血液中の老廃物量の指標となる血清クレアチン値を調べることで、腎臓の機能障害の程度を知り、診断の基準とします。
(※3)東京医大・岡田知也講師らによる調査。第51回日本腎臓学会発表。
病院では尿検査や血液検査などによって、慢性腎臓病の診断がおこなわれます。一般に、慢性腎臓病の診断基準とは、次のようなものです。
1. 尿検査などで腎臓に明らかな障害が認められる。
2. 腎臓の機能が健康な人の60%未満である。
この両方、またはいずれかの状態が3カ月以上続いている。
この基準を満たしていない場合でも、高血圧や糖尿病などがあるとリスクが高いと判断されます。
一般の高血圧治療と同様、食塩をできるだけ控えることが大切です。ただし、腎臓機能がかなり低下していたり、高齢者の場合などは、急激に食塩制限をすると逆に悪化させることもあるので、医師の指導を受けるようにしましょう。
たんぱく質を多くとると老廃物が増え、腎臓に大きな負担がかかります。尿たんぱく量が多い場合、たんぱく質の1日の摂取量は標準体重1kg当たり 0.6~0.8gに制限されます。体重70kgだと1日42~56gと、かなりの少量です。たんぱく質を減らすとエネルギー不足になりがちなので、高エネルギーの炭水化物や脂肪を上手にとる工夫が大切です(ただし、肥満気味の場合は、摂取エネルギーを控える必要があるので、医師の指導にしたがってください)。
腎臓の機能が低下するとカリウムがうまく排出できず、危険な状態になることもあります。慢性腎臓病では、1日当たりのカリウム摂取量が1500mg 以下に制限されます。カリウムは塩分の排出に有効なので、高血圧の人には大切な栄養分ですが、腎臓機能の保護には障害になることもあるので医師と相談しましょう。
タバコは血圧を上昇させて腎臓に負担をかけるため、慢性腎臓病の大きなリスクとなります。また、動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳卒中の原因ともなります。節煙ではなく、きちんと禁煙をしましょう。
※このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。